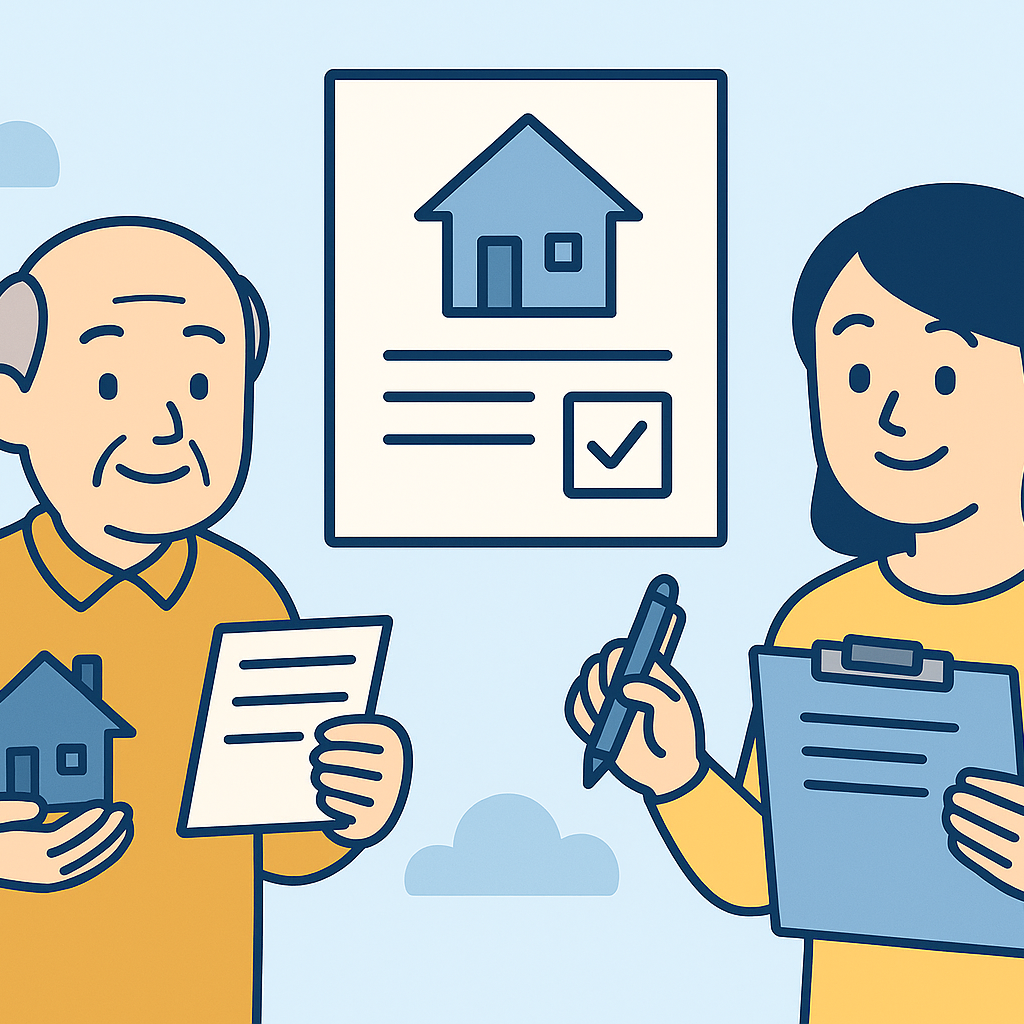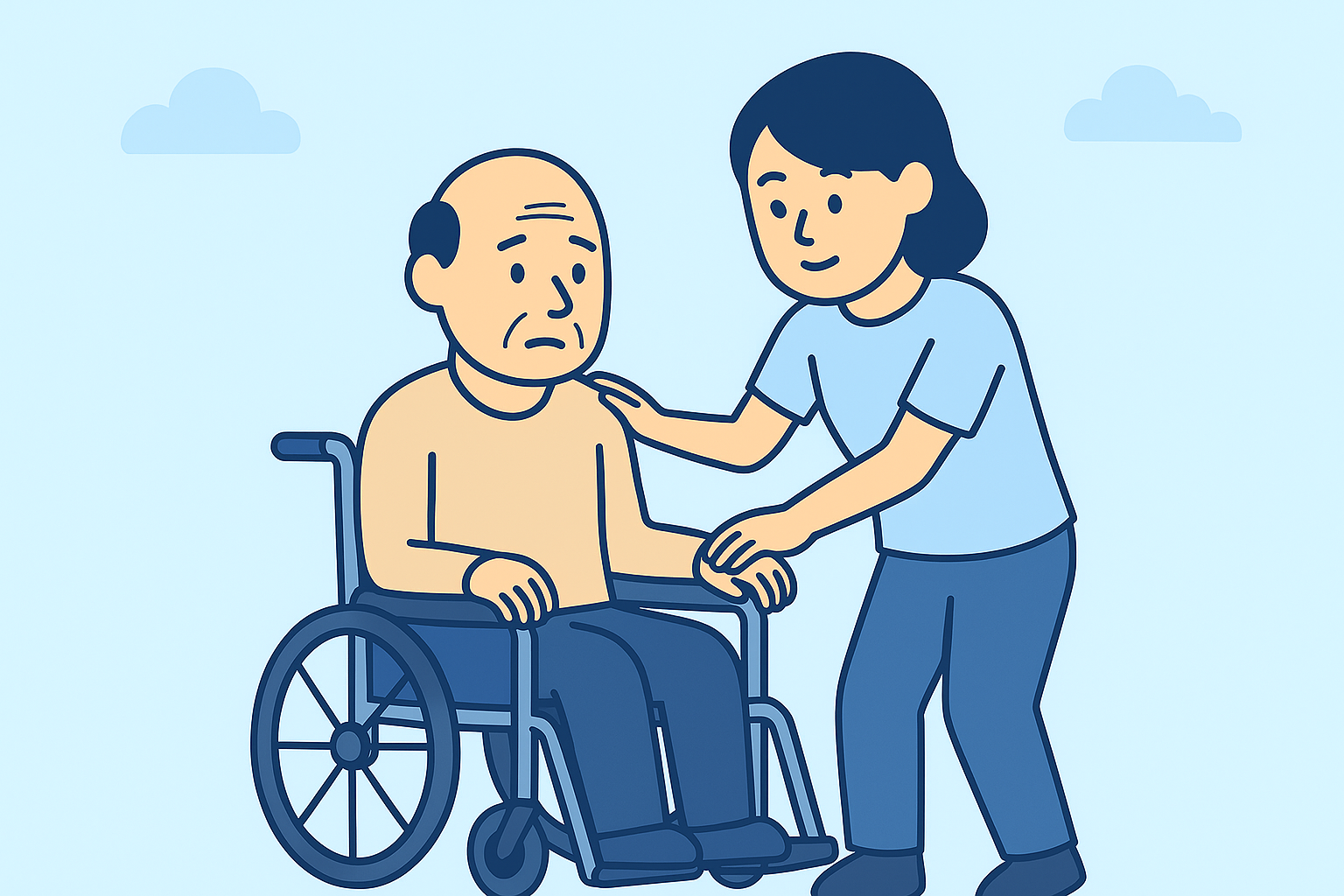
はじめに:介護の貢献と相続の配分にギャップがある現実
親の介護は、身体的にも精神的にも大きな負担を伴います。長期間にわたり仕事や生活の一部を犠牲にしながら介護を担った人にとって、「その努力が相続で報われてほしい」と願うのは自然な感情です。
しかし、現行の民法では、相続人は原則として法定相続分に従って平等に財産を分けるため、介護の有無や負担の大きさは直接的には反映されません。結果として、介護を全くしていなかった兄弟姉妹と同じ相続分になることが多く、不公平感が生まれます。
このギャップを是正するために設けられているのが「寄与分制度」です。この記事では、寄与分の仕組みと実務での扱い、そして公平な相続を実現するためのポイントを解説します。
1. 寄与分とは?民法で認められる評価制度
寄与分とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に、その貢献度を相続分に上乗せできる制度です。民法第904条の2に規定されており、寄与分が認められると、他の相続人より多くの財産を受け取ることが可能になります。
例えば、親の介護を長期間行い、施設費や介護サービス費用を負担せずに済んだことで財産が減らなかった場合、それは財産維持への貢献とみなされます。
2. 認定される寄与行為の範囲(介護・金銭支援・事業貢献など)
寄与分として評価される行為には、介護だけでなく様々な形があります。主なものは次の通りです。
- 療養看護型:長期間にわたる介護や看病。訪問介護サービスの代わりを務めた場合など。
- 金銭支援型:生活費や事業資金を無償で援助し、財産の維持に寄与した場合。
- 事業従事型:被相続人が営む事業に無償または低賃金で長期従事し、利益を支えた場合。
- 財産管理型:不動産や資産運用を無償で管理し、価値を維持または向上させた場合。
介護の場合、短期間の手伝いや日常的な見守り程度では寄与分が認められにくく、「相当程度の期間と労力をかけたか」が重要な判断基準になります。
3. 寄与分を主張するにはどうすればいいか
寄与分を認めてもらうには、相続人間の協議で合意するか、家庭裁判所に「寄与分の額の決定」を申し立てる方法があります。主張の際には、以下のような証拠が必要です。
- 介護日誌やシフト表
- 医療機関や介護サービス事業者とのやり取り記録
- 同居や通院付き添いの証拠(交通費領収書、写真など)
- 被相続人の財産維持に関するデータ(預金残高推移など)
証拠が不十分だと、寄与分は認められにくくなります。感覚的な主張ではなく、客観的資料の準備が鍵です。
4. 実務では“寄与分の認定”が難しい理由
寄与分制度は存在していても、実務上は認定されにくいのが現実です。その理由は次の通りです。
- 介護の程度や期間の立証が困難
- 他の相続人が貢献の評価に納得しない
- 民法が想定する「特別な寄与」のハードルが高い
- 介護の代替費用をどの程度とみなすかで争いが生じる
また、寄与分は「寄与がなければ財産が減っていた」ことの証明も必要なため、金額換算が難しく、申立後に長期化することも多いです。
5. 遺言書に介護者への配慮を明記する重要性
寄与分の認定は手続きが複雑で、相続人間の合意も難しいため、最も確実な方法は遺言書に介護者への配慮を明記しておくことです。遺言書で「長女には介護の貢献を考慮し、法定相続分に○○万円を加えて相続させる」といった形で明記すれば、寄与分の争いを避けられます。
特に公正証書遺言であれば、形式不備や無効リスクが低く、相続開始後すぐに効力を発揮できます。
6. 相続人間での合意形成のポイント
介護をめぐる感情的対立を避けるためには、次のような工夫が有効です。
- 生前から介護の分担や評価方法を家族で話し合う
- 資産内容や介護状況を定期的に共有する
- 中立的な第三者(ケアマネジャー、専門家)を交えて議論する
特に介護の負担は一部の家族に偏りがちです。役割分担や将来の相続における評価を事前にすり合わせておくことで、後々の不満を減らせます。
まとめ:親の想いを“明文化”することが最も公平
親の介護に尽くした人の努力を相続に反映させるには、寄与分制度がありますが、実務的なハードルは高めです。確実に公平性を担保するには、生前に遺言書で意思を明確にし、家族間で資産と介護状況を共有しておくことが最も有効です。
介護はお金だけでなく時間や感情の大きな負担を伴うものです。その貢献を正しく評価するためには、「法律上の制度」だけでなく「親自身の言葉」と「家族の合意」が欠かせません。