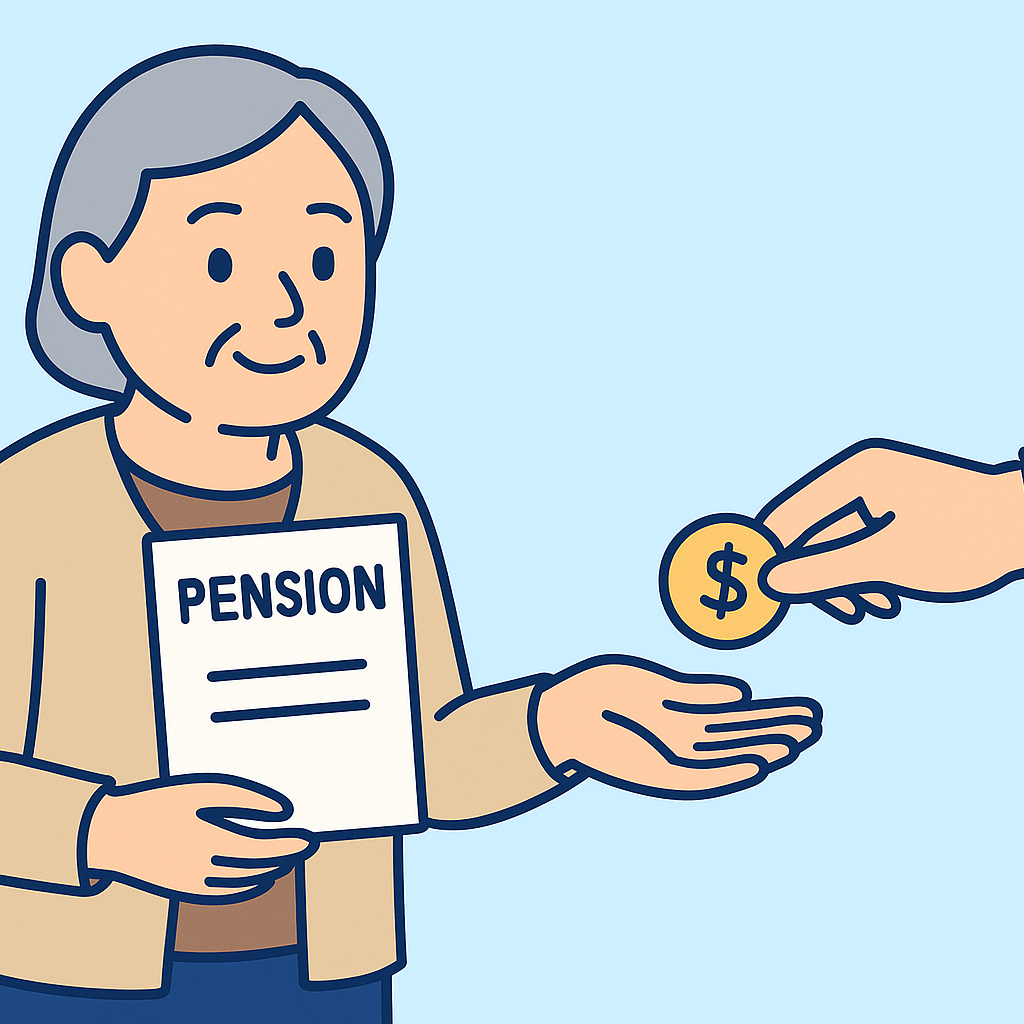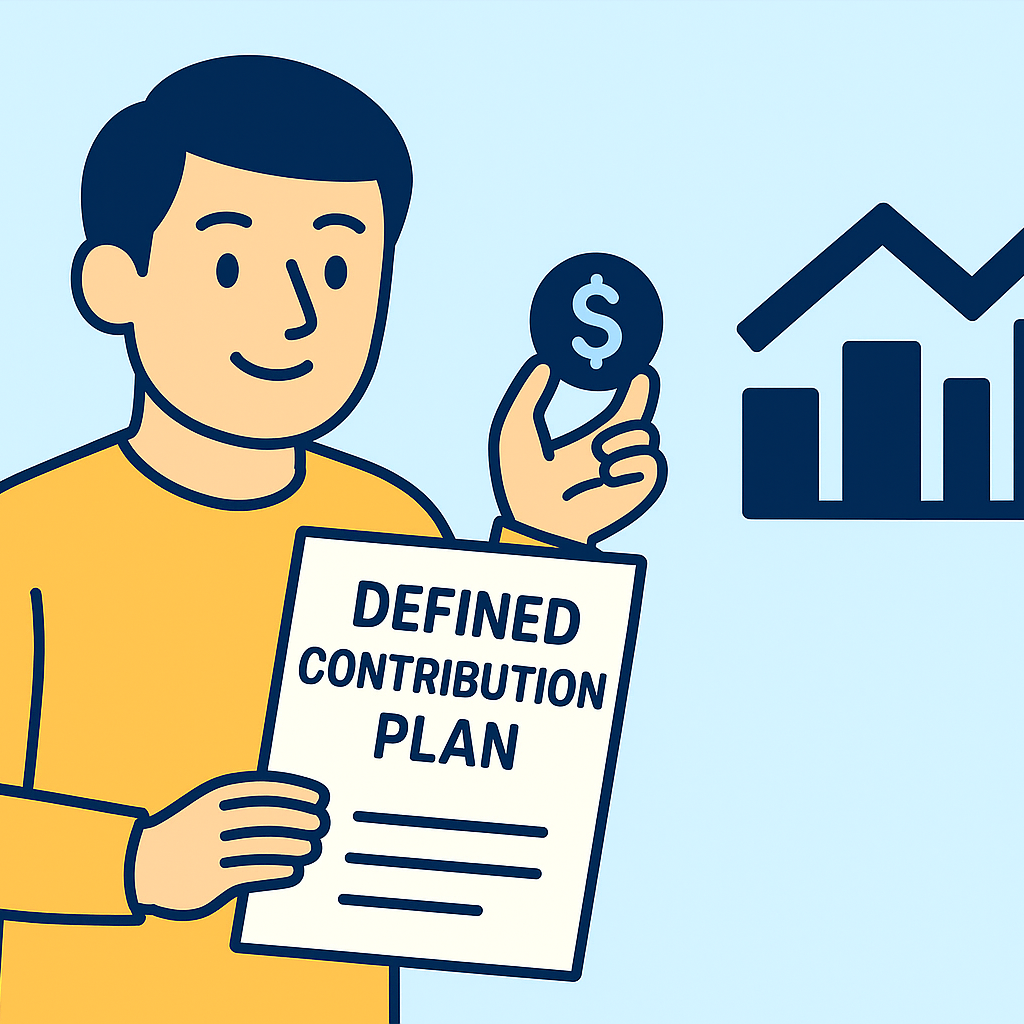はじめに:第3号被保険者という仕組み
日本の公的年金制度には「第1号・第2号・第3号」という3つの被保険者区分があります。その中で「第3号被保険者」というのは、主に専業主婦や短時間労働のパートで扶養に入っている配偶者が対象となる特別な制度です。自分で保険料を納めなくても、配偶者(多くは会社員や公務員)の厚生年金に扶養されることで国民年金に加入した扱いとなり、将来の基礎年金を受け取ることができます。
この仕組みは、家庭における役割分担を前提として整備されたものですが、働き方が多様化した現代においては「保険料を払っていないのに年金がもらえるのは不公平では?」といった議論が生じることもあります。専業主婦や扶養に入っている配偶者にとって、第3号被保険者制度の理解は、老後の備えを考えるうえで欠かせません。
1. 第3号被保険者とは?対象条件
第3号被保険者は、公的年金制度における被保険者区分のひとつです。対象となるのは以下の条件を満たす人です。
- 厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者。
- 年収が130万円未満(一定の条件では106万円未満)で、かつその収入で生計を立てていない人。
- 20歳以上60歳未満であること。
つまり、典型的には「会社員の夫に扶養されている専業主婦(またはパート勤務で一定以下の収入)」がこれに該当します。
2. 保険料負担がない仕組み
第3号被保険者の大きな特徴は、自分で保険料を支払う必要がないことです。
国民年金の保険料は通常、月額約17,000円(2025年度水準)を納める必要がありますが、第3号被保険者はこの負担が免除され、国民年金に加入しているものと同じ扱いを受けます。
この仕組みは、配偶者が厚生年金に加入し保険料を納めていることを前提に、「世帯単位」で年金制度を支える考え方から成り立っています。
3. 将来の年金額にどう反映されるか
第3号被保険者であった期間は、国民年金の納付済み期間としてカウントされます。したがって、40年間すべてを第3号で過ごした場合でも、老齢基礎年金を満額受給することが可能です。
ただし、厚生年金に加入しているわけではないため、将来受け取れるのは基礎年金のみです。平均的な年金額は年間約80万円(月額6.6万円程度)となり、厚生年金に加入していた人に比べると受給額は少なくなります。
4. 夫婦の働き方で変わる年金制度
夫婦の働き方によって、受け取る年金額には差が生じます。
| 夫婦の働き方 | 夫の年金額 | 妻の年金額 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 夫:厚生年金 妻:第3号被保険者 | 約200万円 | 約80万円 | 約280万円 |
| 共働き夫婦(夫婦ともに厚生年金) | 約200万円 | 約150万円 | 約350万円以上 |
| 自営業世帯(夫婦とも国民年金のみ) | 約80万円 | 約80万円 | 約160万円 |
このように、同じ夫婦でも働き方によって老後の収入差が大きくなります。
5. 130万円・106万円の壁との関係
第3号被保険者に関連してよく話題になるのが「年収の壁」です。
- 130万円の壁: 配偶者の扶養に入れるかどうかの基準。これを超えると扶養から外れ、自分で国民年金・健康保険に加入する必要が出てきます。
- 106万円の壁: 一定規模以上の企業で働く場合、年収が106万円を超えると厚生年金に加入義務が発生します。
この収入基準を意識して働き方を調整している人も多いですが、長期的に見ると「厚生年金に加入して自分で年金額を増やす」という選択が老後資金の安定につながることもあります。
6. 就業によって第3号を外れるケース
次のような場合、第3号被保険者から外れます。
- 年収が基準額(130万円または106万円)を超えた場合。
- 配偶者が失業や自営業転身などで厚生年金の資格を失った場合。
- 自分が60歳を迎えた場合(第3号は20〜60歳が対象)。
外れた場合は、自分で国民年金保険料を納めるか、勤務先で厚生年金に加入する必要があります。切り替え手続きを怠ると「未納」扱いとなり、将来の年金額が減るリスクがあります。
7. 年金見込額での専業主婦世帯の特徴
第3号被保険者として長期間過ごした場合、年金額は基礎年金分のみとなるため少なめです。しかし、夫が厚生年金に加入していれば、世帯単位では一定の安定収入を確保できます。
一方、夫が退職後に早く亡くなった場合は、妻が受け取れるのは遺族年金に限られるため、生活水準が大きく下がるケースもあります。専業主婦世帯は「夫婦で一緒にいる間は安心感があるが、片方を失うと収入が大幅に減るリスクがある」という特徴を持っています。
8. 誤解されやすいポイントと注意点
第3号被保険者に関しては、よく誤解される点があります。
| 誤解 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「保険料を払っていないのに年金をもらえる」 | 実際には配偶者の厚生年金保険料に含まれて制度が支えられている。 |
| 「専業主婦は何も手続きしなくても自動的に年金がもらえる」 | 実際には扶養に入る際に届出が必要。 |
| 「一度第3号に入れば一生安心」 | 収入や状況によって外れる可能性がある。 |
これらの誤解を放置すると、将来の年金に不利益が生じることもあります。正しい知識を持ち、必要な手続きを怠らないことが重要です。
まとめ:働き方と年金の関係を正しく理解
第3号被保険者制度は、専業主婦や扶養内で働く配偶者にとって大きなメリットを持つ仕組みです。保険料を負担せずに国民年金の加入期間を積み立てられるため、老後の基礎的な生活保障を確保できます。
一方で、基礎年金のみでは老後資金として十分とは言えず、世帯の状況次第では将来的に収入が大幅に減るリスクもあります。扶養に入るか自分で働いて厚生年金に加入するかは、老後の安心に直結する重要な選択です。
大切なのは「現在の負担の軽さ」だけで判断するのではなく、「将来の年金額」「夫婦のライフプラン」「長生きリスク」を踏まえて考えることです。第3号被保険者の仕組みを正しく理解し、適切な選択を行うことで、より安定したセカンドライフにつなげることができるでしょう。