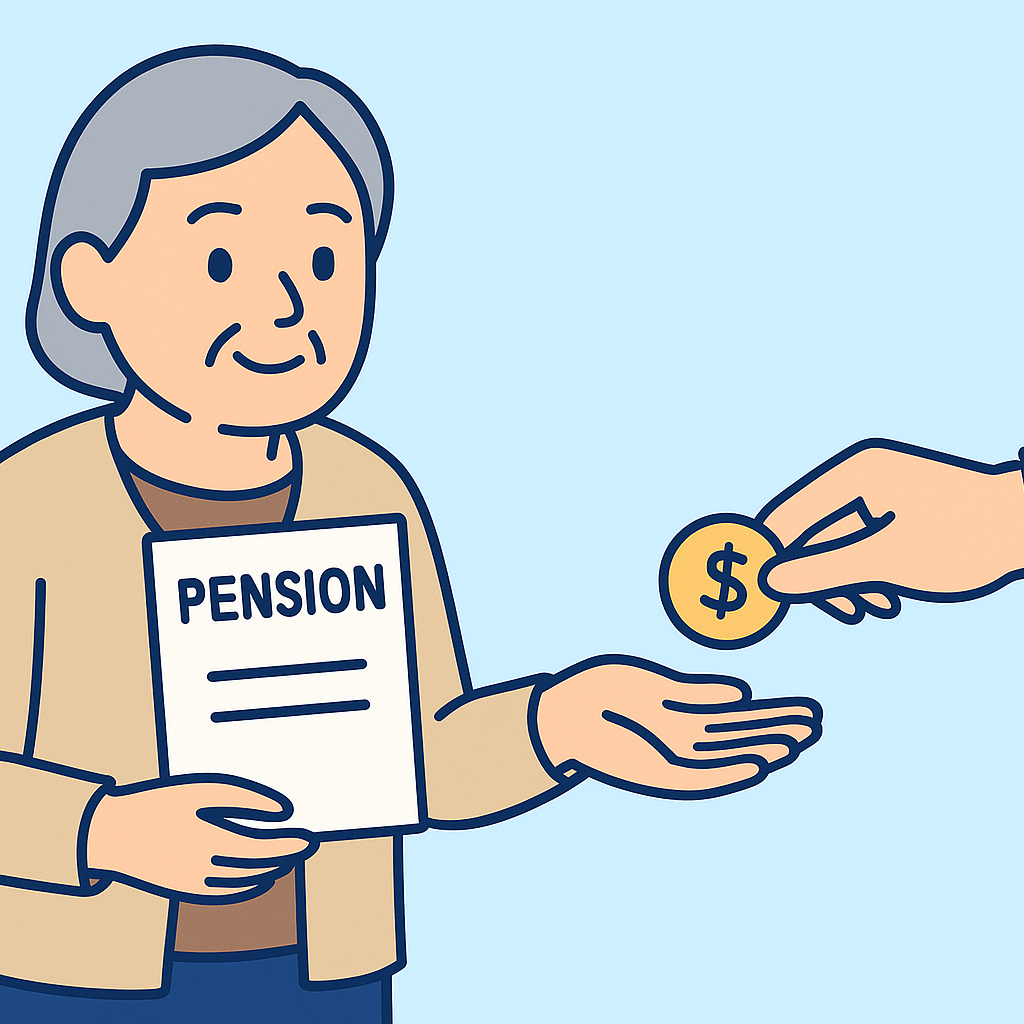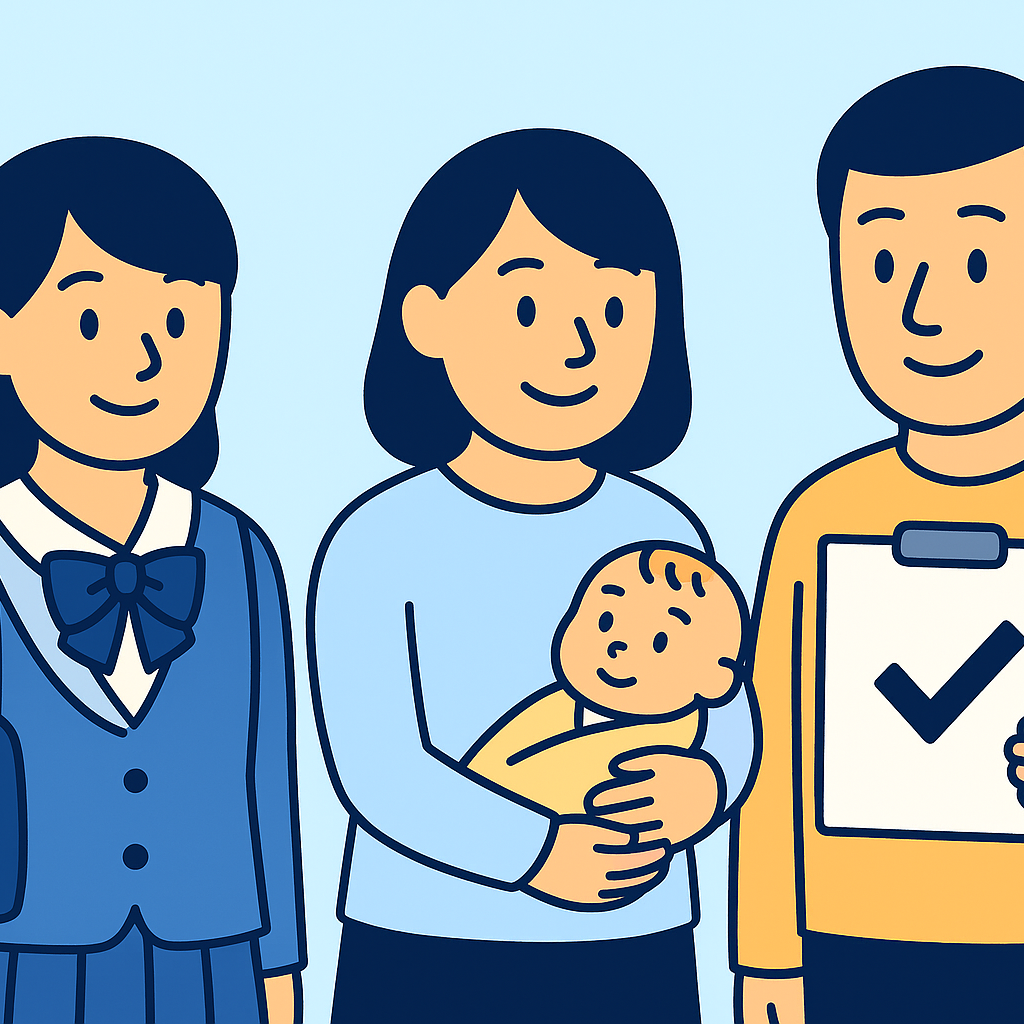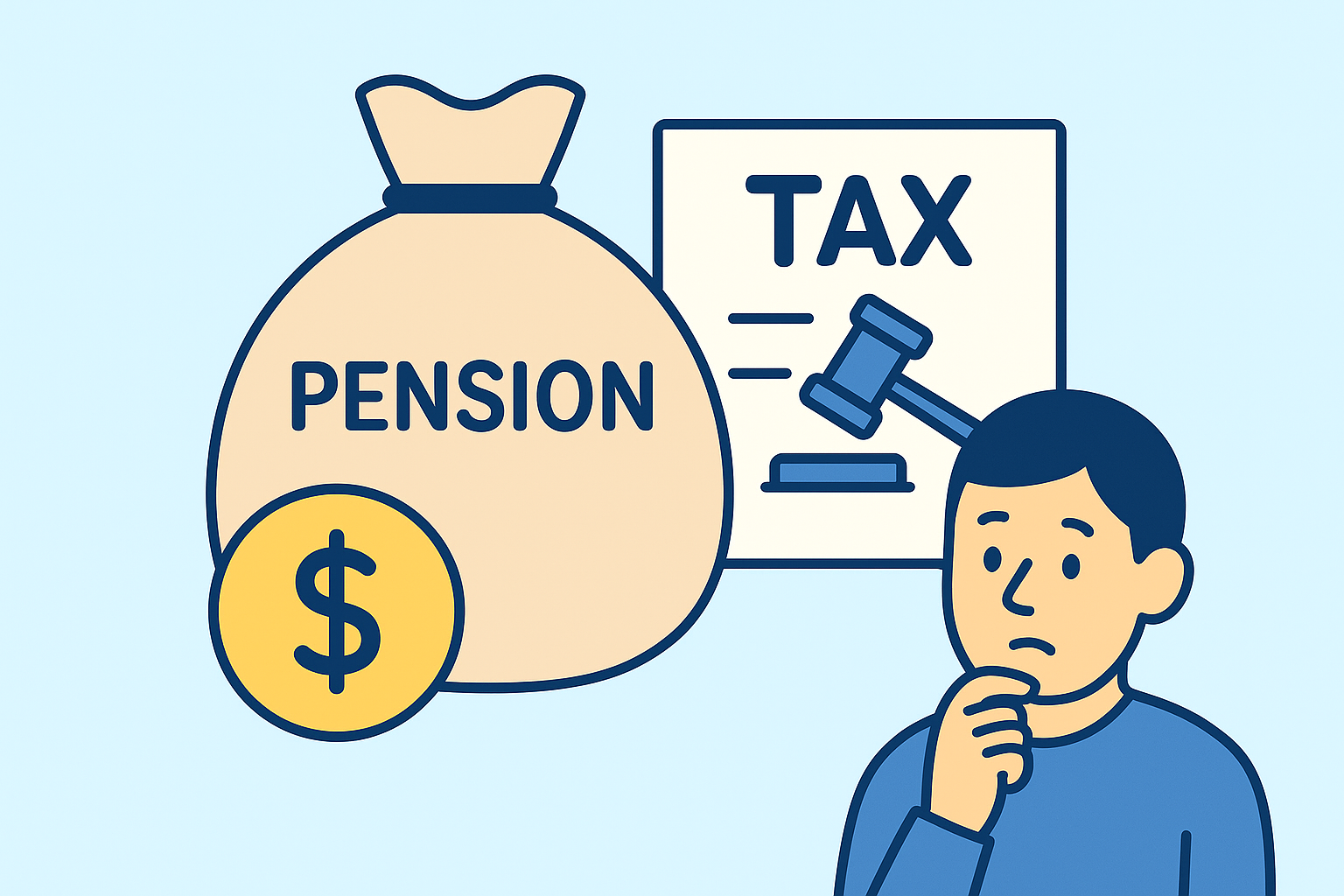
はじめに:年金と税金の関係を正しく理解
「年金は非課税だから安心」と思っている方は少なくありません。しかし、年金はれっきとした「収入」であり、一定額を超えると課税対象になります。特に高齢期は、公的年金以外にパート収入や不動産収入、投資収益なども合わさり、思った以上に税負担が生じるケースがあります。さらに、年金からは介護保険料や国民健康保険料が天引きされるため、「手取り額」と「額面」に差が出ることも見逃せません。
この記事では、年金と税金・社会保険料の関係を整理し、老後の資金計画に役立つ知識を解説します。
1. 公的年金等控除の仕組み
年金収入はそのまま課税されるのではなく、「公的年金等控除」という制度を通じて課税所得が計算されます。これは、年齢や年金額に応じて一定額を差し引いてから課税する仕組みです。
65歳以上の場合
| 受け取る年金額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|
| 330万円以下 | 110万円 |
| 330万円超〜410万円以下 | (年金額 × 25%)+ 27万5千円 |
| 410万円超〜770万円以下 | (年金額 × 15%)+ 68万5千円 |
| 770万円超〜1,000万円以下 | (年金額 × 5%)+ 145万5千円 |
| 1,000万円超 | 195万5千円 |
65歳未満の場合
| 受け取る年金額 | 公的年金等控除額 |
|---|---|
| 130万円以下 | 60万円 |
| 130万円超〜410万円以下 | (年金額 × 25%)+ 27万5千円 |
| 410万円超〜770万円以下 | (年金額 × 15%)+ 68万5千円 |
| 770万円超〜1,000万円以下 | (年金額 × 5%)+ 145万5千円 |
| 1,000万円超 | 195万5千円 |
このように、年金額が少ない場合は非課税になりますが、年金額が大きくなるにつれて控除額は相対的に縮小していきます。
2. 所得税がかかるケースとかからないケース
年金に対して所得税がかかるかどうかは、年金額とその他の所得によって決まります。
所得税がかからないケース
- 単身で年金収入のみ、年間110万円以下(65歳以上の場合)。
- 扶養控除や基礎控除を適用すると、さらに非課税枠が広がる。
所得税がかかるケース
- 年金収入が大きい人。
- 年金に加え、給与・不動産収入・投資収入がある場合。
3. 住民税の課税条件
収入が公的年金等のみである世帯の住民税の非課税限度額は、年齢や扶養親族の有無、収入や居住地などによって異なります。特に、世帯主が65歳未満か65歳以上かで控除額が大きく変わるため注意が必要です。ここでは例として「東京都港区(1級地)」での算出例を紹介します。
65歳未満の場合(公的年金等控除額:60万円)
単身世帯では、45万円+60万円=105万円まで非課税です。扶養親族がいる場合は次のとおりです。
| 同一生計配偶者・扶養親族の人数 | 前年の公的年金等収入金額(非課税限度額) |
|---|---|
| 0人(本人のみ) | 105万円以下 |
| 1人 | 161万円以下 |
| 2人 | 196万円以下 |
| 3人 | 231万円以下 |
| 4人 | 266万円以下 |
65歳以上の場合(公的年金等控除額:110万円)
単身世帯では、45万円+110万円=155万円まで非課税です。扶養親族がいる場合は次のとおりです。
| 同一生計配偶者・扶養親族の人数 | 前年の公的年金等収入金額(非課税限度額) |
|---|---|
| 0人(本人のみ) | 155万円以下 |
| 1人 | 211万円以下 |
| 2人 | 246万円以下 |
| 3人 | 281万円以下 |
| 4人 | 316万円以下 |
住民税は前年の所得に基づいて計算され、課税対象を超えると所得割+均等割が課されます。所得税と異なり定額部分(均等割)があるため、少額の年金受給者でも負担が発生することがあります。
4. 年金から天引きされる社会保険料(介護保険料など)
年金を受け取るときには、実際に手取り額が減る要因として「社会保険料の天引き」があります。
- 介護保険料:65歳以上は原則徴収対象。所得に応じて月数千円〜1万円以上。
- 国民健康保険料(後期高齢者医療保険料):年金額や世帯所得に応じて算出。
- 所得税・住民税:特別徴収として年金から天引きされる。
そのため、額面の年金収入が200万円でも、実際の手取りは社会保険料や税金を引いた後で180万円程度に減ることもあります。
5. 年金受給額と確定申告の要否
年金収入がある場合、確定申告が必要かどうかは次の基準で判断されます。
- 年金収入が400万円以下で、かつ他の所得が20万円以下 → 確定申告不要(年末調整のように源泉徴収される)。
- 年金収入が400万円超、または他の所得が20万円超 → 確定申告が必要。
ただし、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)を受けたい場合は、自主的に確定申告をする方が有利になります。
6. パート収入・不動産収入との合算課税
年金以外にパート収入や不動産収入がある場合、それらは合算されて課税対象となります。
- 年金収入150万円+パート収入100万円 → 合計250万円として課税判定。
- 不動産収入がある場合も同様に合算。
そのため「年金だけなら非課税だったのに、パート収入を得たら課税対象になった」というケースも少なくありません。老後も働く場合や副収入がある人は、税負担を計算に入れる必要があります。
7. 税金を軽減する方法(控除・医療費控除など)
年金生活者でも、工夫次第で税金を軽減できます。
- 配偶者控除・扶養控除を利用する。
- 医療費控除:年間10万円超の医療費を支払った場合に適用(高齢者は対象になりやすい)。
- 社会保険料控除:自分や家族の保険料を支払った場合。
- 寄付金控除(ふるさと納税):節税と返礼品で実質的な生活補助につながる。
こうした控除を活用することで、課税所得を減らし、所得税や住民税を軽減できます。
8. 税金対策を踏まえた老後の資金計画
老後の資金計画を立てるときは、年金額の「額面」だけでなく「税金や社会保険料を引いた後の手取り」を基準にすることが大切です。
- 年間年金収入が200万円でも、住民税・介護保険料などで20万円程度引かれ、実際の手取りは180万円前後になる。
- パート収入を加えた結果、課税対象が増え、社会保険料も高くなる可能性がある。
- 節税対策を組み合わせれば、可処分所得を増やすことが可能。
まとめ:年金は非課税ではなく課税対象になることを理解
年金は老後の生活を支える重要な収入ですが、税金や社会保険料がかかるため「額面=手取り」ではありません。
- 公的年金等控除により一定額までは非課税だが、超えれば課税対象。
- 住民税や介護保険料が加わり、実際の手取りはさらに減る。
- パート収入や不動産収入と合算され、課税負担が増えることもある。
- 控除や医療費控除、ふるさと納税を活用すれば軽減可能。
老後の資金計画では「年金の手取り額」を正しく把握し、税金・社会保険料を含めた家計シミュレーションを行うことが不可欠です。年金と税金の関係を理解しておくことで、不安を減らし、安心したセカンドライフに備えることができます。