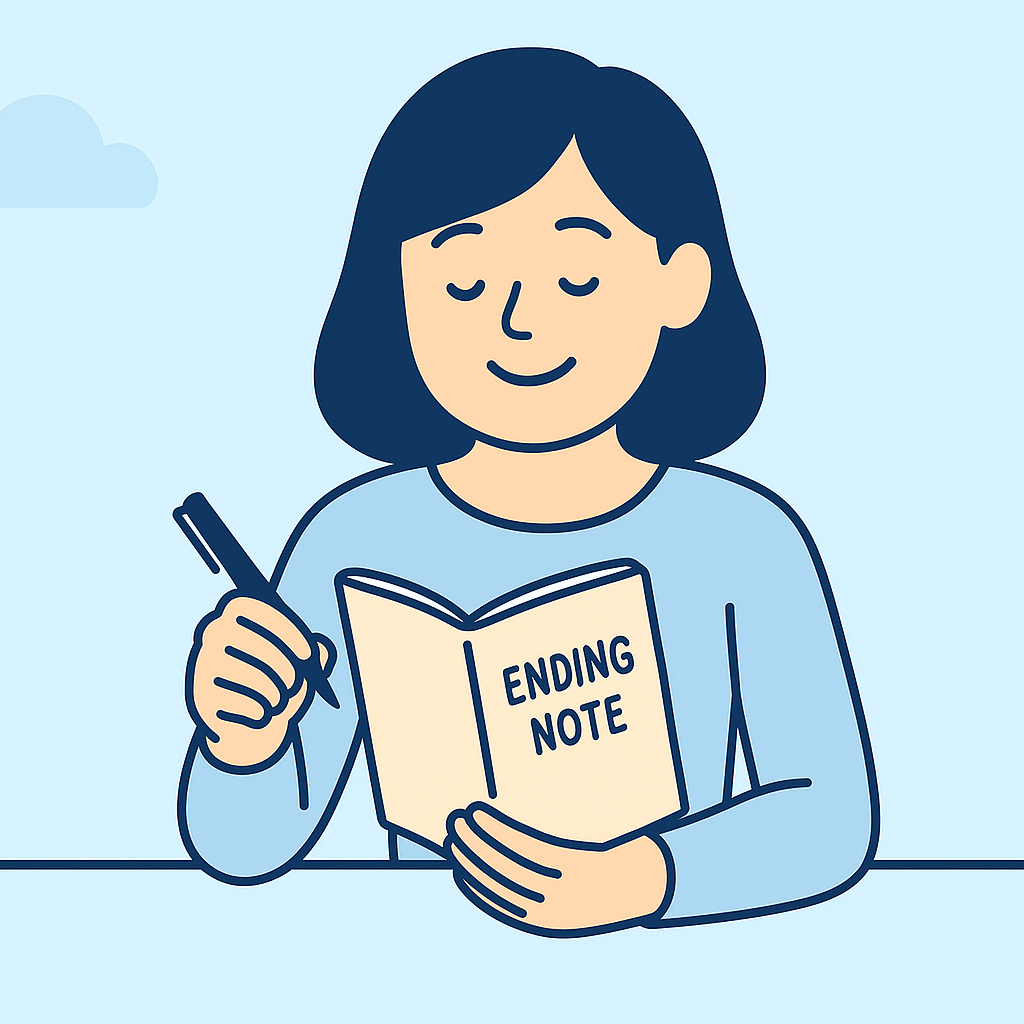はじめに:空き家の増加と社会的背景
日本では今、空き家の数が年々増加しています。総務省の統計によると、全国の空き家は900万戸以上となっています。
背景には、高齢化や地方の人口減少、都市部への人口集中などの要因があり、相続によって発生した実家の空き家を「使わず放置している」家庭が少なくありません。しかし、この「放置」には大きな落とし穴があります。
特に深刻なのが、特定空き家に指定されることによって、固定資産税が6倍に跳ね上がるリスクです。本記事では、空き家を相続した場合に注意すべきポイントと、損失を回避するための対策を整理します。
1. 相続後に空き家になるケースの実情
相続した不動産が空き家になるパターンは主に以下の3つです。
- 親が住んでいた家を相続したが、自分は別の場所に住んでいる
- 兄弟で共有相続し、利用・売却の方針が決まらない
- とりあえずそのままにしておこうと保留される
相続した直後は、気持ちの整理も必要で、すぐに決断できないこともあります。しかし、数カ月、数年と経過するうちに、気がつけば管理もされず、荒れ放題の空き家になっていたというのはよくある話です。
空き家が長期間放置されると、劣化が進み、防犯や景観上の問題も発生。やがて自治体から「特定空き家」の認定を受けるリスクが生じます。
2. 「特定空き家」とは?自治体の判断基準
「特定空き家」とは、2015年に施行された空家等対策特別措置法に基づき、自治体が危険・衛生・景観などの観点から指定する状態の空き家です。
以下のような状態が基準とされています:
- 倒壊や保安上の危険がある
- 著しく衛生上有害(ゴミの放置、害虫発生など)
- 著しく景観を損なっている
- 適切な管理がされていない状態が明らか
特定空き家に指定されると、所有者に改善の勧告や命令が出され、それでも対応しないと税制上の優遇措置が撤廃されることになります。
3. 勧告を受けた場合のデメリット(税優遇の撤廃)
通常、住宅が建っている土地には住宅用地特例が適用され、固定資産税が最大で1/6まで軽減されます。しかし、特定空き家に「勧告」が出されると、この特例が外されてしまい、固定資産税が6倍に跳ね上がる可能性があります。
たとえば、通常であれば年3万円で済んでいた固定資産税が、いきなり18万円になる、といったことも。
また、都市計画税の軽減措置も失われ、実質的な維持コストが一気に増加します。このため、空き家をただ所有しているだけでも、大きな経済的負担となるのです。
4. 管理が不十分な空き家に対する行政代執行
勧告や命令に従わず、空き家が放置されたまま改善されない場合、自治体は行政代執行として、所有者の許可なく家屋を解体・撤去することができます。
もちろん、その費用は所有者に請求されます。費用は数十万円から数百万円にもなる可能性があり、さらに不動産の価値も失われることになります。
また、登記簿上は親名義のままでも、相続人が管理責任を問われるため、「名義変更していない=無関係」という逃げ道は通用しません。
5. 空き家活用・売却・解体の判断基準
空き家をどう扱うかは、その立地・状態・資産価値・感情的な要素などで異なりますが、主な選択肢は以下の3つです。
- 売却する:資産価値が残っているうちに現金化。管理の手間からも解放される
- 活用する:賃貸・店舗転用・セカンドハウスなどで収益化を目指す
- 解体する:税優遇が外れても、更地として売却・活用しやすくする
重要なのは、「今は使わないから放置する」ではなく、3年後、5年後の使い方を逆算して判断することです。
6. 空き家バンクや自治体支援制度の活用方法
最近では、空き家の利活用を支援する取り組みも各地で進んでおり、代表的なものが空き家バンクです。
空き家バンクとは、自治体やNPOが仲介役となり、売却や賃貸を希望する空き家と、利用希望者をマッチングする仕組みです。手数料が安く済み、地域とのつながりも作りやすいのが特徴です。
また、以下のような支援制度もあります:
- 解体費用の一部補助
- 改修・リフォーム費用の助成
- 賃貸化支援(保証制度の導入など)
活用できる制度は地域ごとに異なるため、まずは自治体の窓口に相談することが第一歩です。
まとめ:「放置せず、早めの活用・処分」が資産を守る
空き家は、相続した人が何もしなければ、「資産」から「負債」へと変貌する可能性の高い存在です。特定空き家に認定されれば、固定資産税の増加だけでなく、行政による強制措置や地域とのトラブルにもつながります。
だからこそ、空き家を相続したら「すぐに動く」が鉄則です。使うか、売るか、解体するか。迷っている間にも劣化と課税は進みます。
活用できる制度や専門家のサポートを最大限に活用し、“持ち続ける”か“手放す”かの意思決定を早めに行うことが、資産を守る最良の策となります。