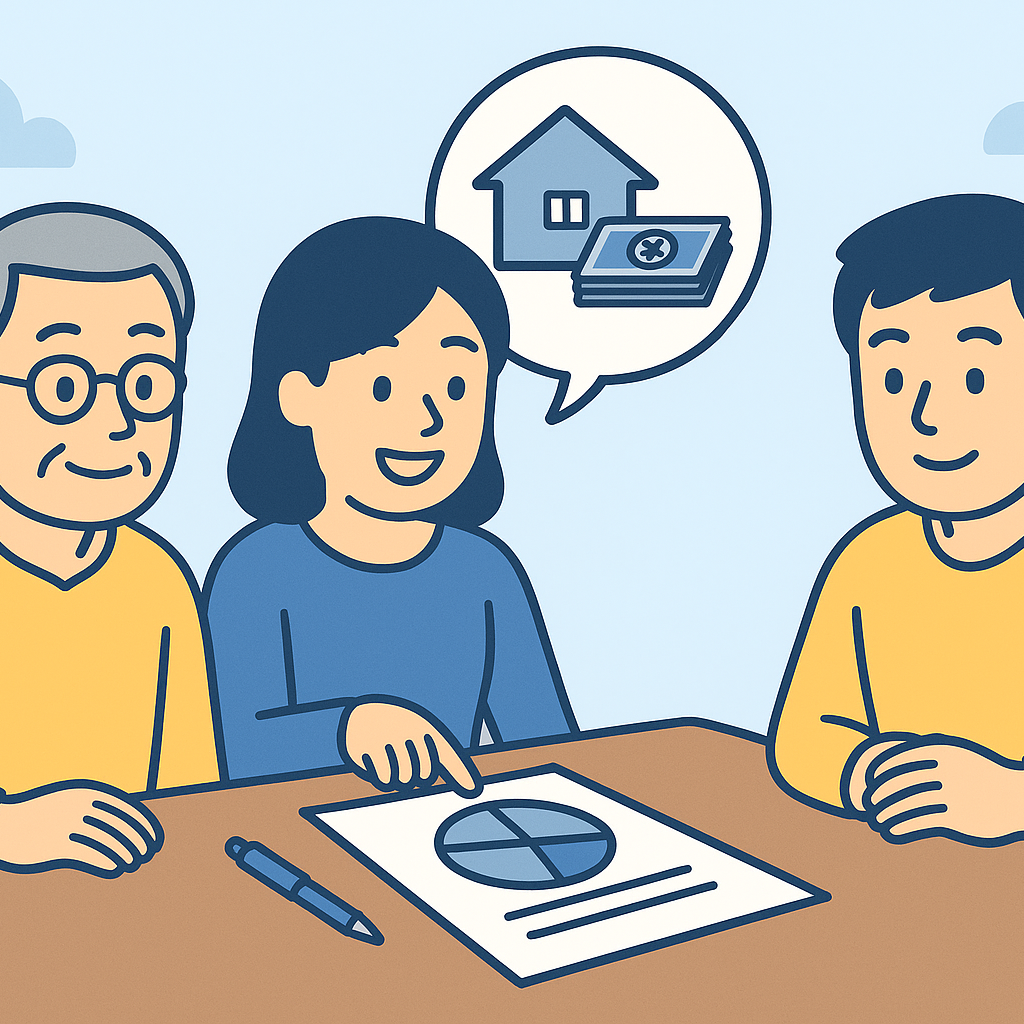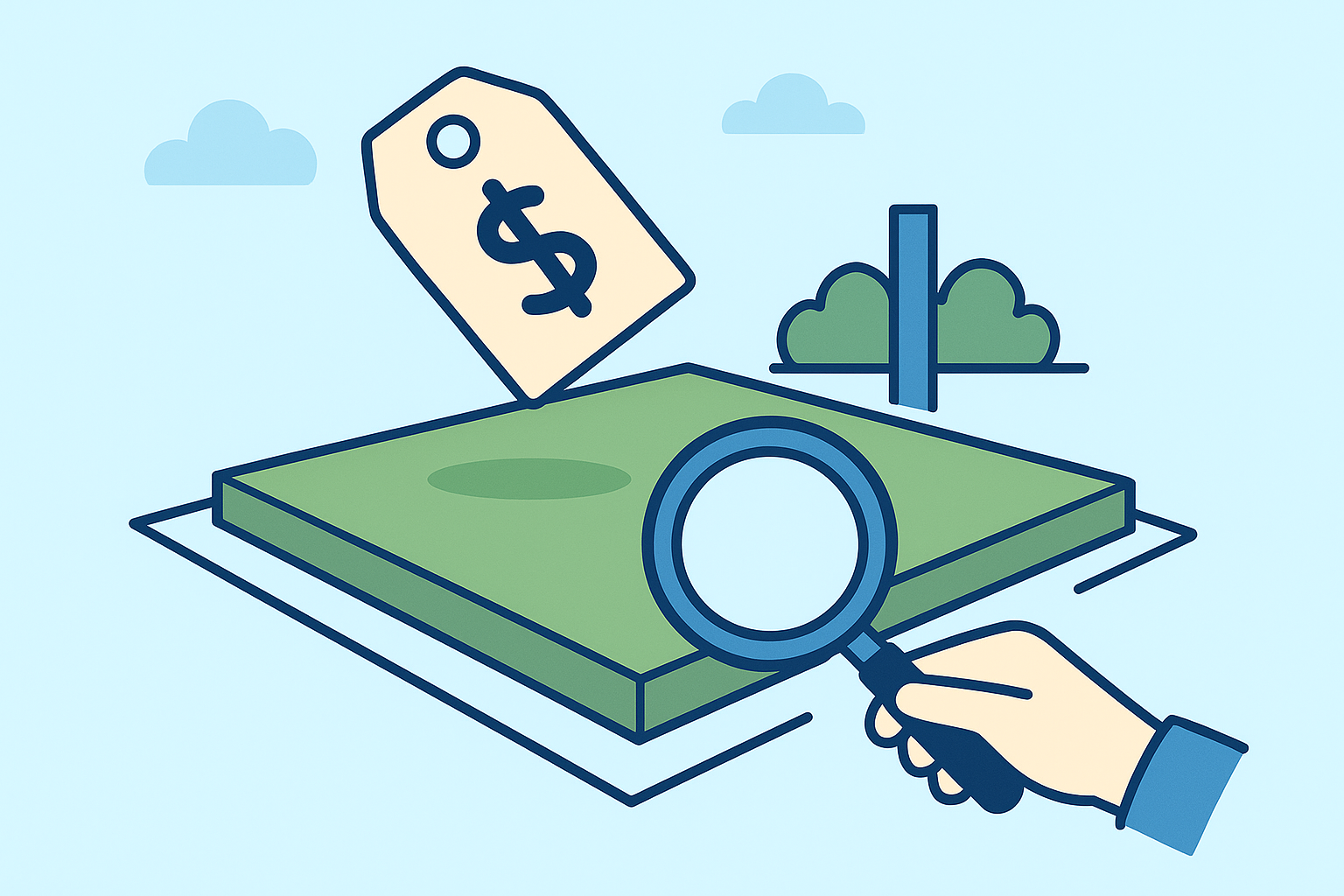
はじめに:なぜ複数の評価額があるのか?
相続や不動産の取引に関わると、「同じ土地や建物なのに評価額が違う」という場面によく出くわします。例えば、相続税の計算では「路線価」、固定資産税の納付書には「固定資産税評価額」、不動産会社が提示する査定書には「実勢価格(時価)」が載っていることがあります。しかも、それぞれの金額は大きく異なります。
これは、評価の目的や基準が違うためです。税金の計算のための評価なのか、市場での売買を想定した評価なのか、または自治体が課税のために決めた評価なのかによって、算定方法も金額も変わってきます。
相続対策を考える上では、「どの評価額がどの目的で使われるのか」を正しく理解しておくことが欠かせません。この記事では、代表的な評価方法である「路線価」と「固定資産税評価額」、そして実勢価格との違いを詳しく解説し、相続時の不動産評価のポイントを押さえます。
1. 相続税評価に使われる「路線価」とは
路線価とは、国税庁が毎年公表する、道路(路線)に面する標準的な宅地1㎡あたりの価格です。相続税や贈与税の計算の際に基準となります。具体的には、土地が面している道路ごとに「○○円/㎡」と定められ、その価格に土地の面積を掛けて評価額を算出します。建物の評価は別途「固定資産税評価額」を用いるため、土地と建物で評価基準が異なります。
路線価はあくまで「課税のための評価額」であり、実際の市場価格(実勢価格)よりも低く設定されているのが一般的です。平均的には実勢価格の70〜80%程度が目安とされています。例えば、実勢価格が1㎡あたり50万円の土地でも、路線価は35万円程度というケースは珍しくありません。相続税はこの路線価をもとに計算されるため、市場価格より低く評価される分、結果として納税額が実勢価格ベースよりも抑えられることがあります。
2. 固定資産税評価額の用途と特徴
固定資産税評価額は、市町村(または東京都の場合は都)が固定資産税や都市計画税を課税するために、3年ごとに見直して決定する評価額です。評価基準は「固定資産評価基準」という総務省の規定に基づき、原則として時価の70%程度とされています。
固定資産税評価額は毎年4月頃に送付される「固定資産税納税通知書」に記載されています。用途は主に次の通りです。
- 固定資産税・都市計画税の課税
- 登録免許税の計算(相続登記や売買時)
- 不動産取得税の計算
相続税計算には直接使いませんが、建物の評価や、登録免許税・不動産取得税の算定には欠かせない数値です。路線価と比べると、評価額は低めになります。
3. 実勢価格(時価)とのギャップが生む影響
実勢価格(時価)とは、実際に市場で取引されるときの価格を指します。売買事例や不動産業者の査定などから導き出され、需要と供給によって変動します。
実勢価格は景気や地域の人気度、土地の形状や接道条件などによって大きく変わるため、税務評価額(路線価や固定資産税評価額)とは大きな差が生じることがあります。
この差が、相続や贈与の戦略に影響します。例えば、実勢価格が高いエリアでは、路線価や固定資産税評価額との差を利用して相続税を抑えることが可能です。一方、実勢価格が低下している地域では、税務評価が実勢価格より高くなってしまい、納税負担が割高になることもあります。
4. 路線価方式と倍率方式の違い
土地の相続税評価は、原則として路線価方式で行われますが、路線価が設定されていない地域では「倍率方式」が使われます。
- 路線価方式:土地が面する道路ごとに設定された路線価をもとに評価。都市部や人口の多い地域で採用。
- 倍率方式:固定資産税評価額に国税庁が定める倍率(地域ごとに異なる)を掛けて評価。地方や路線価未設定の地域で採用。
倍率方式は路線価方式に比べて評価の細かさが劣りますが、計算は簡単です。固定資産税評価額がベースになるため、結果的に路線価方式よりも評価額が低くなるケースもあります。
5. 評価額を下げる工夫:借地権・貸家建付地の評価
相続税の節税のためには、土地の評価額を適正かつ低く抑える工夫が有効です。その代表例が「借地権割合」や「貸家建付地の評価」です。
- 借地権割合:他人に貸している土地(借地)の場合、借地人の権利があるため評価額は減額されます。
- 貸家建付地:土地の上に貸家が建っていて賃貸中の場合、借家人の権利(借家権)があるため、土地の評価額を減額できます。
これらの減額規定を活用すると、同じ面積・同じ場所の土地でも評価額が大きく下がり、相続税の負担が軽くなります。ただし、適用条件や計算方法は複雑で、専門家による確認が必要です。
6. 不動産評価でミスが起きる典型的な例
相続の現場では、不動産評価に関するミスが原因で不要な税金を払ってしまうケースがあります。代表的な例は次の通りです。
- 用途地域や接道条件を誤って評価:実際より高い路線価を適用してしまう。
- 借地権や貸家建付地の減額を適用し忘れる。
- 私道や崖地など、利用制限のある土地の評価減を見落とす。
- 倍率地域で倍率を誤って計算。
こうしたミスを避けるには、相続税申告を得意とする税理士や不動産鑑定士のチェックが有効です。特に土地の形状や法規制が特殊な場合は、標準的な計算だけでは正確な評価ができません。
まとめ:目的に応じて「正しい評価額」を選ぶことが重要
不動産には、路線価、固定資産税評価額、実勢価格といった複数の評価額が存在し、それぞれの算出方法や用途が異なります。
- 路線価:相続税・贈与税の基準
- 固定資産税評価額:固定資産税・都市計画税、登記税の基準
- 実勢価格:市場取引や売却価格の目安
相続対策や売却、税金計算など、目的によってどの評価額を基準にするかが変わるため、「一番高い額=正しい額」ではありません。むしろ、目的に沿った評価額を正しく選ぶことが、税負担を減らし、資産を守る鍵になります。
早い段階から評価額の違いを理解し、必要に応じて専門家の助言を受けながら、自分にとって最も有利な形で不動産を活用・承継していきましょう。