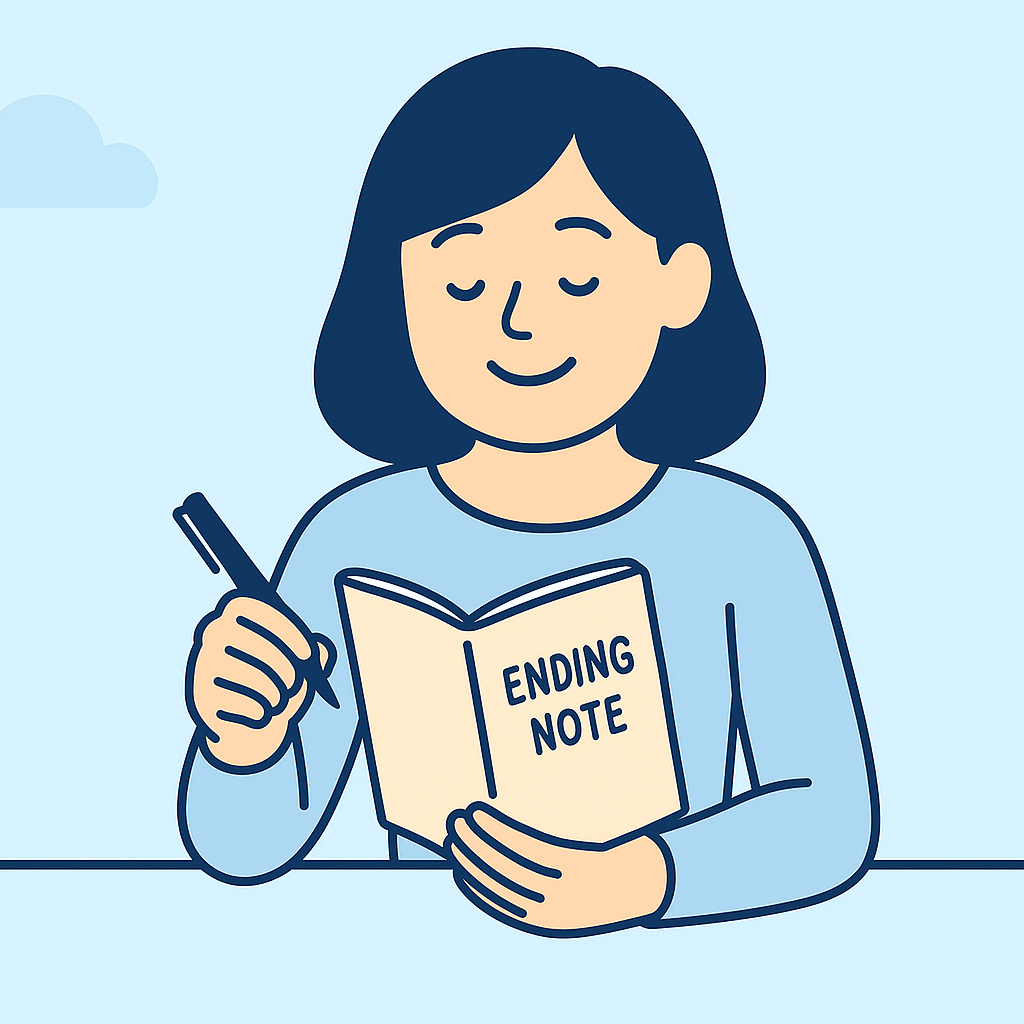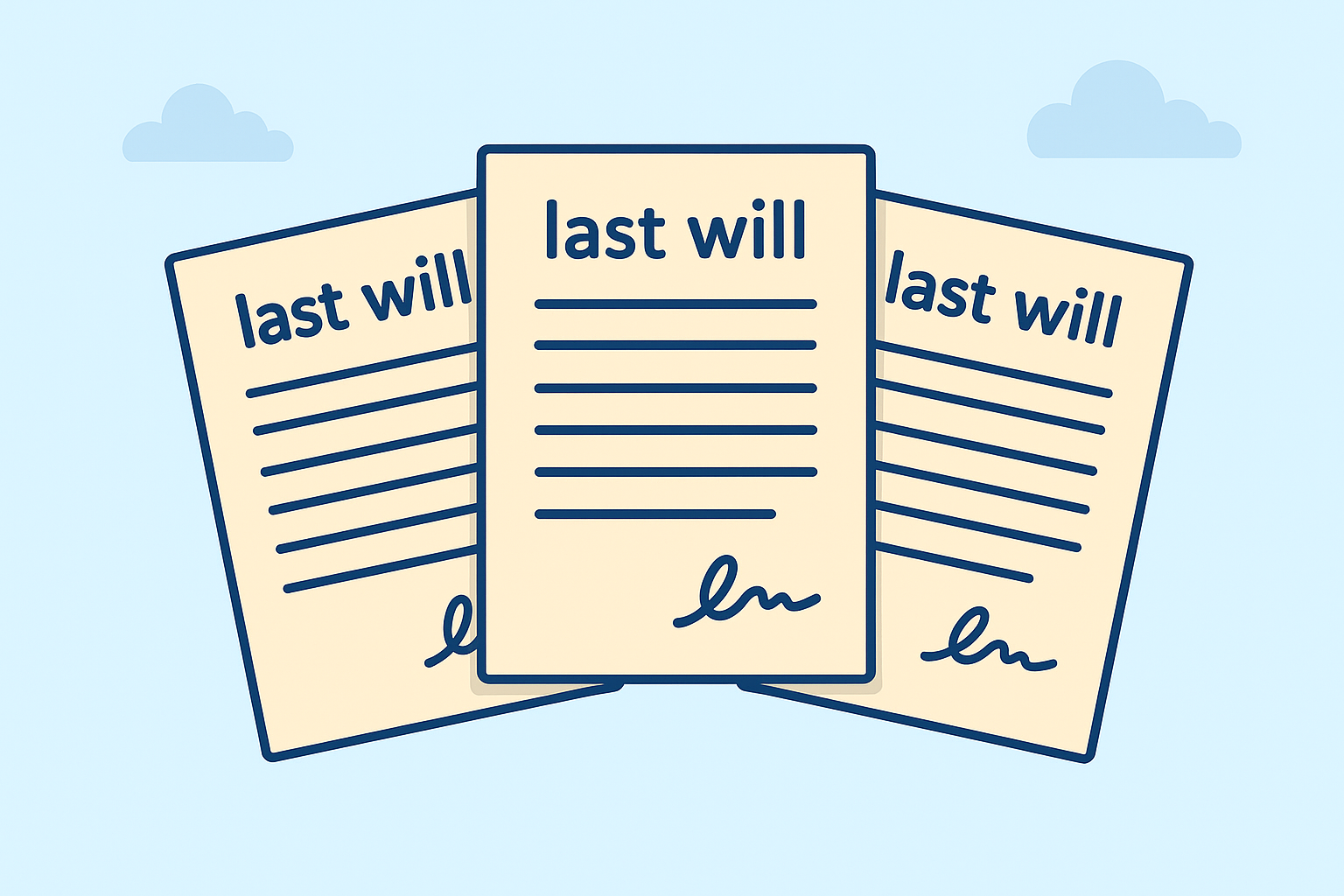
はじめに:なぜ複数の遺言書が存在することがあるのか
遺言書は、作成した時点の意思を反映するものですが、人の意思や状況は時間とともに変わるものです。
たとえば、資産の内容が変わった、相続人との関係が変化した、税制改正があったなどの理由で、遺言書を書き直すことがあります。
また、遺言者本人が複数の形式で遺言を残してしまうこともあり、自筆証書遺言と公正証書遺言が両方見つかる、といったケースも珍しくありません。
こうした場合、複数の遺言書が全て有効なのか、一部が無効になるのか、どちらを優先するのかが問題になります。誤った判断をすると、相続人間の争いを招く可能性が高くなります。
この記事では、複数の遺言書が見つかった場合の有効性判断の基本ルールと、トラブルを避けるためのポイントを解説します。
1. 遺言書の種類と法的効力(自筆・公正証書・秘密証書)
遺言書には主に次の3種類があります。
- 自筆証書遺言:遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印したもの。保管方法によっては家庭裁判所の検認が必要です。2020年からは法務局での保管制度も始まり、保管された場合は検認不要になります。
- 公正証書遺言:公証人が遺言者の口述をもとに作成し、公証役場で保管するもの。法的効力が高く、偽造や紛失のリスクが低いのが特徴です。検認不要。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま、公証役場で存在だけを証明してもらう形式。公証人は内容を確認しないため、形式的な不備や無効リスクが高いとされます。
形式により信頼性や効力の安定性は異なりますが、いずれも民法に定められた要件を満たせば有効です。
2. 複数ある場合の原則は「日付が新しいものが有効」
民法では、複数の遺言書が存在し、その内容が抵触・矛盾している場合は、日付が新しい遺言書を優先すると定められています。
これは、人の意思は時間の経過とともに変わり得るため、最後に作成された遺言が遺言者の最終意思と考えられるからです。
例えば、2018年に作成した自筆証書遺言と、2022年に作成した公正証書遺言があり、内容が異なる場合は、原則として2022年の遺言書が有効となります。
ただし、古い遺言書の一部が新しい遺言書と矛盾しない場合、その部分は引き続き有効になることもあります。
3. 一部が矛盾するケースの扱い
複数の遺言書があっても、すべての内容が矛盾するとは限りません。
たとえば、古い遺言書には「長男に自宅を相続させる」と記載され、新しい遺言書には「次男に別荘を相続させる」と記載されている場合、両者に矛盾はないため、両方の遺言が有効になります。
しかし、同じ財産について異なる指定がある場合は、新しい遺言書の記載が優先され、古い記載はその範囲で効力を失います。
この判断には遺言内容の詳細な比較が必要であり、場合によっては専門家の助言を受けることが望まれます。
4. 遺言書が無効とされる代表的なケース
複数の遺言書があっても、その一部または全部が無効とされる場合があります。主な理由は次の通りです。
- 方式違反:自筆証書遺言で日付が欠けている、押印がないなど。
- 作成時の意思能力の欠如:認知症が進んで判断能力がなかった場合。
- 内容の不明確さ:財産や受取人が特定できない記載。
- 法律上無効な内容:相続人の廃除や負担付遺贈の条件が不適法など。
特に方式違反は形式面のミスで無効になるため、形式要件の確認は非常に重要です。
5. 偽造・強要などが疑われる場合の対応
複数の遺言書がある場合、そのうちの1通について「偽造ではないか」「無理やり書かされたのではないか」という疑いが生じることもあります。
この場合、相続人や利害関係人は家庭裁判所に遺言無効確認の訴えを提起できます。偽造・変造が認められれば、その遺言書は無効になります。
また、筆跡鑑定や医療記録の開示などによって、作成時の状況を証明する必要があります。疑念を放置すると、後の手続き全体が停滞する可能性が高まります。
6. 家庭裁判所の検認と遺言執行者の役割
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として開封前に家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認は遺言の存在と内容を確認する手続きで、遺言の有効・無効を判断する場ではありません。
一方、公正証書遺言は検認不要で、直ちに執行できます。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための権限を持つ人物で、遺言書で指定された場合や、家庭裁判所が選任する場合があります。複数の遺言書がある場合でも、最新の有効な遺言書に基づき執行します。
まとめ:トラブルを避けるためには「明確さ」と「一貫性」がカギ
複数の遺言書が存在すると、相続手続きが複雑化し、相続人間の不信感を招きやすくなります。
原則として最新日付の遺言書が有効ですが、矛盾しない部分は古い遺言書も効力を持ちます。形式面の不備や偽造・強要の疑いがあれば、無効となる可能性もあります。
トラブル防止のためには、
- 1つの有効な遺言書に集約すること
- 作成・保管方法を明確にすること
- 内容を一貫させること
が重要です。特に、公正証書遺言を利用すれば形式不備や紛失・改ざんのリスクを大幅に減らせます。遺言は「書くだけで安心」ではなく、「最新の意思を明確に残す」ことが最も大切です。