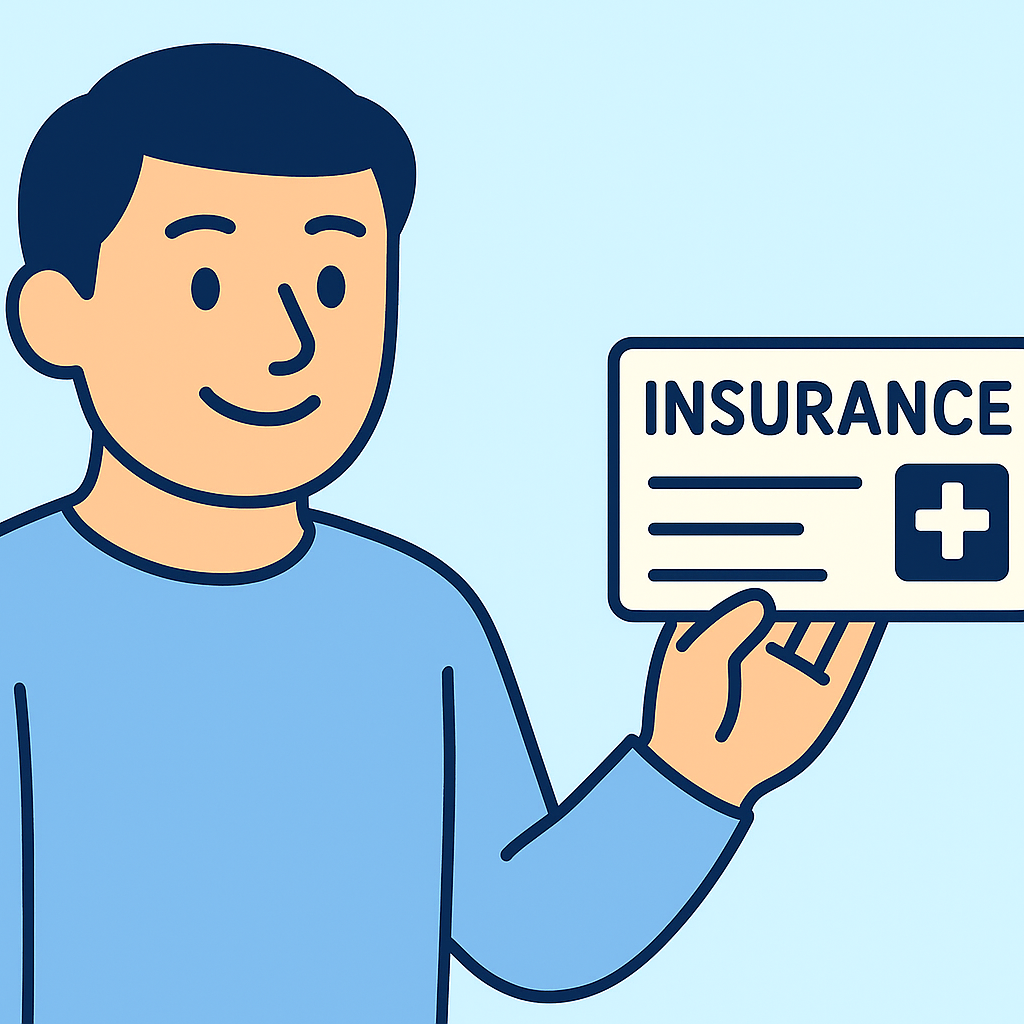はじめに
会社員や自営業者を問わず、私たちが生活していく上で欠かせないのが「健康保険」です。病気やケガで医療機関を受診すると、実際に支払う金額が3割負担で済むのは健康保険に加入しているからです。しかし、健康保険制度は無料ではなく、毎月の給与や所得から「保険料」を支払うことで成り立っています。
健康保険料は一律の金額ではなく、年収や家族構成によって変わります。とくに会社員と自営業者(国民健康保険加入者)では計算方法が異なり、同じ年収でも負担額に大きな差が出ることがあります。さらに、扶養家族がいるかどうか、ボーナスの有無、臨時収入などによっても変動するため、正確に把握していないと家計の計画が狂うことになりかねません。
この記事では、会社員と自営業者それぞれの保険料計算の仕組みを解説し、具体的に年収300万円、500万円、800万円のケースを取り上げてシミュレーションします。健康保険料を正しく理解することで、家計管理や将来設計に役立てましょう。
1. 会社員の保険料計算の基本(標準報酬月額)
会社員の健康保険料は、給与明細に「社会保険料」として記載されています。これは健康保険と厚生年金などがセットで控除されており、健康保険料は標準報酬月額という基準によって計算されます。
標準報酬月額は、実際の給与を一定の幅で区分したものです。たとえば給与が28万円なら「標準報酬月額28万円」の区分に当てはめ、そこに保険料率を掛けて保険料が決まります。保険料率は協会けんぽの場合、都道府県ごとに異なりますがおおむね9〜10%前後で、その半分を会社が、残り半分を従業員が負担します。
概念的には、会社員は給料の約5%程度を毎月健康保険料として負担している、と捉えるとイメージしやすいでしょう(地域や組合により変動)。
2. 国民健康保険の計算の基本(所得割・均等割)
自営業者やフリーランス、退職後に国保に加入する人の保険料は国民健康保険(国保)として市区町村ごとに計算されます。方式は自治体で異なりますが、基本構成は次の通りです。
- 所得割:前年の所得に一定割合を乗じる
- 均等割:加入者1人あたり定額で加算
- 平等割:1世帯あたり定額で加算
- 資産割:一部自治体で固定資産額に応じて加算
国保は前年所得が基準となるため、退職して収入がなくても前年の収入が高ければ翌年の保険料は高額になることがあります。逆に、所得が低ければ軽減措置が適用されやすい仕組みです。
3. 扶養がある場合の違い
会社員の健康保険(被用者保険)と国民健康保険では、扶養家族の扱いが異なります。
- 会社員(社会保険):配偶者や子どもを被扶養者にしても、保険料は増えません。年収130万円未満(等)の条件を満たせば、扶養家族は自己負担なしで保険証を持てます。
- 国民健康保険:扶養という概念はなく、家族一人ひとりが被保険者。加入者が増えるごとに均等割が人数分加算され、保険料は世帯人数に連動して増えます。
同じ4人家族でも、会社員の健康保険と自営業者の国保で負担が大きく異なるのは、この仕組みの差が理由です。
4. 年収300万・500万・800万のケース比較
ここでは、年収別に会社員と国保の健康保険料をシミュレーションした目安を示します(協会けんぽ<東京都>、国保は標準的な自治体を想定)。
| ケース | 前提 | 保険料の目安 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 年収300万円(会社員) | 独身/標準報酬月額:25万円前後 | 約12,000〜13,000円/月(本人負担) | 会社と折半後の自己負担分 |
| 年収300万円(国保) | 独身/均等割あり | 年間:約25万〜30万円(≒月2万円前後) | 自治体により差あり |
| 年収500万円(会社員) | 扶養2人/標準報酬月額:40万円前後 | 約20,000円/月(本人負担) | 扶養がいても保険料は変わらない |
| 年収500万円(国保) | 世帯3人(本人+扶養2人) | 年間:約45万〜55万円(≒月4万円前後) | 均等割で人数分加算 |
| 年収800万円(会社員) | 扶養2人/標準報酬月額:65万円前後 | 約32,000円/月(本人負担) | 扶養分もカバーされ割安感 |
| 年収800万円(国保) | 世帯3人 | 年間:約80万〜100万円(≒月7万〜8万円) | 所得割+均等割の影響大 |
同じ年収でも「会社員か自営業者か」で負担は大きく異なります。扶養家族が多いほど差が拡大する点に注意が必要です。
5. ボーナスや臨時収入の影響
会社員の場合、ボーナスにも健康保険料がかかります。標準賞与額に保険料率を掛け、会社と折半で負担します。たとえばボーナス100万円なら、そのうち数万円が社会保険料として控除されます。
国保の場合は、ボーナスや臨時収入が翌年の所得に反映されます。退職金や副業収入などで前年所得が上がると、翌年の国保料は増加します。つまり、国保は「今の収入」ではなく「前年の収入」が影響するのが特徴です。
6. 保険料を確認する方法
「自分はいくら払うのか」を把握するには、以下を確認しましょう。
| 加入区分 | 確認先 | ポイント |
|---|---|---|
| 会社員(協会けんぽ/組合健保) | 給与明細の社会保険料欄/協会けんぽ・組合の保険料率表 | 標準報酬月額と賞与額に料率を適用。本人負担は概ね「料率の半分」。 |
| 国民健康保険 | 市区町村からの納付通知書/自治体サイトの試算ツール | 前年所得・世帯人数・軽減適用の有無で変動。自治体差が大きい。 |
概算は自力計算も可能ですが、扶養人数や軽減措置の影響が大きいため、最終確認は公式情報で行いましょう。
7. 家計管理に活かすシミュレーション活用法
健康保険料は固定費の一部。将来の負担増を見込んでシミュレーションしておくことが重要です。
- 年収アップ時:社会保険料の増加で可処分所得は想定より伸びないことがある。
- 自営業者:収入変動が大きい場合、前年所得ベースの国保料を想定して貯蓄計画を。
- ライフイベント:扶養の増減・副業収入の有無ごとに見直しを。
まとめ:収入に応じた保険料負担を把握して安心
健康保険料は年収や加入区分、家族構成で大きく変わります。
- 会社員:標準報酬月額に基づき算定、会社が半分負担。
- 国保:所得割・均等割などで算定、人数が増えるほど負担増。
- 共通:年収が高いほど負担は上昇。ボーナス/臨時収入も影響。
具体例の比較からも、同じ年収でも加入区分で数十万円規模の差が生じ得ます。定期的にシミュレーションして、家計への影響を把握しておくことが安心につながります。