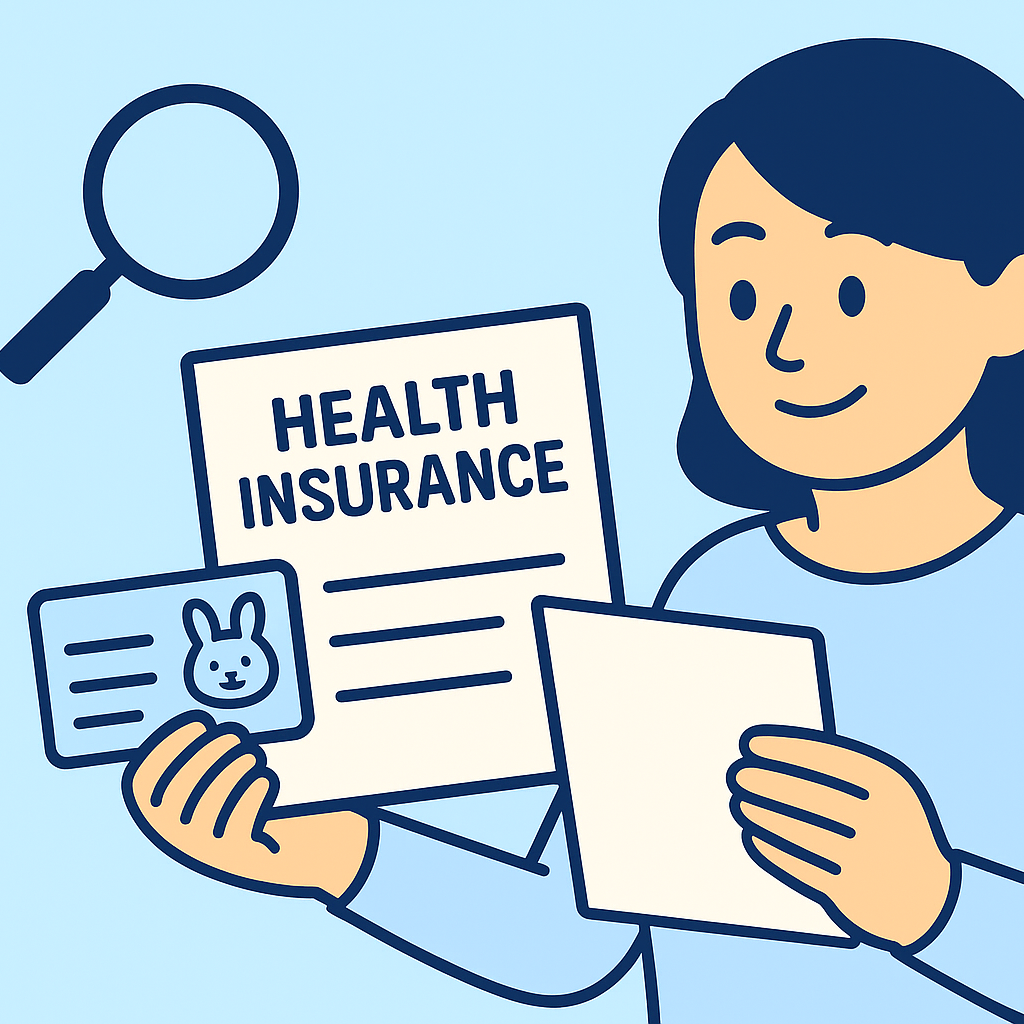はじめに
多くの会社員は60歳前後で定年退職を迎えます。再雇用制度を利用して働き続ける方もいれば、完全に仕事を離れて年金生活に入る方もいるでしょう。いずれの場合でも、退職後は会社の社会保険から外れるため、新たな健康保険への加入が必要です。
定年後は医療を利用する機会が増える年代に入ります。保険制度の選択を誤ると、保険料負担が大きくなったり、保障内容に不安が残ったりすることもあります。特に75歳からは「後期高齢者医療制度」に切り替わりますが、それまでの期間をどうつなぐかが重要です。ここでは、定年退職後から75歳までの健康保険の選択肢や注意点を整理して解説します。
1. 任意継続制度を利用する場合のポイント
定年退職後にまず検討できるのが「任意継続被保険者制度」です。これは退職前に加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)を最長2年間だけ継続できる制度です。
加入条件は、退職前に継続して2か月以上の被保険者期間があり、退職日から20日以内に申請すること。加入すれば在職中と同じ給付内容が受けられるため、安心感があります。
ただし保険料は全額自己負担になるため、在職中の2倍程度に増えるのが一般的です。標準報酬月額に上限があるため、高所得者だった人にとっては任意継続の方が国民健康保険より安くなる場合がありますが、低所得の場合は国保や扶養の方が有利になることもあります。
2. 国民健康保険に加入する場合の特徴
任意継続を選ばない場合、多くの人は「国民健康保険」に加入します。国民健康保険は市区町村が運営しており、自営業者や無職の人が加入する制度です。
保険料は前年の所得に応じて決まり、世帯単位で請求されます。定年退職後は給与収入が途絶えるため、翌年度以降の保険料は下がる傾向にありますが、退職直後の年度は現役時代の所得を基に計算されるため、意外に高額になるケースもあります。
一方で、自治体によっては「退職者医療制度」や「保険料の軽減措置」が用意されており、失業や退職による所得減少が考慮される場合があります。退職直後の年収が大きく減る人は、市区町村に確認して減免制度を利用できるか調べるとよいでしょう。
3. 家族の扶養に入る条件とメリット
配偶者が会社員や公務員として健康保険に加入している場合、その扶養に入るのも有力な選択肢です。扶養に入ると、自身の保険料を負担する必要がなくなるため、家計の負担を大きく抑えられます。
扶養に入る条件は、年収が130万円未満(60歳以上や障害者の場合は180万円未満)であること、そして被保険者と生計を同じくしていることです。定年退職後に年金を受給する場合、その年金額が基準を超えると扶養に入れないこともあります。特に厚生年金や企業年金を受け取る人は扶養の条件に該当するかどうかを確認する必要があります。
4. 65歳以降の年金との関係
定年退職後、多くの人は65歳から老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取り始めます。年金収入は生活の柱になりますが、その額が扶養判定に影響する点には注意が必要です。
例えば、65歳以降に受け取る年金額が130万円を超える場合、配偶者の扶養には入れません。この場合は国民健康保険に加入することになります。また、年金の受給額はその人の現役時代の収入や加入年数によって大きく異なるため、退職後の健康保険選びには「自分の年金見込額」を踏まえた検討が欠かせません。
5. 医療費負担割合の変化(70歳・75歳での切替)
定年退職後の健康保険を考える上で重要なのが、医療費の自己負担割合の変化です。
- 70歳未満:医療費の自己負担は原則3割
- 70〜74歳:原則2割(現役並み所得者は3割)
- 75歳以降:後期高齢者医療制度に加入し、1割(現役並み所得者は3割)
つまり、退職後の生活では年齢によって自己負担割合が減っていく仕組みがあります。特に70歳以降は医療費の負担が軽くなるため、国保や任意継続の負担が重くても、将来の軽減を見据えて計画することが大切です。
6. 選択肢ごとの費用シミュレーション
退職後の健康保険料は、収入や家族構成によって大きく変わります。以下はあくまで一例ですが、代表的なケースを比較してみます。
- 任意継続:標準報酬月額28万円だった人 → 月額約2万8千円(自己負担)
- 国民健康保険:前年の年収が400万円、夫婦2人世帯 → 月額約3万円
- 扶養:配偶者の会社員保険に入る → 保険料0円
このように、収入や世帯状況によって最も有利な制度は異なります。退職前にシミュレーションを行い、どの選択肢が老後資金にとって負担が少ないかを確認することが重要です。
7. 老後のライフプランに合わせた選び方
健康保険の選択は単なる費用比較ではなく、老後のライフプラン全体に直結します。
- 退職後すぐに再雇用や再就職を予定している場合 → 任意継続や扶養でつなぐ
- 完全リタイアして年金生活に入る場合 → 国民健康保険や扶養が中心
- 年金額が大きく扶養に入れない場合 → 国保が基本になる
さらに、医療の利用頻度や将来の介護リスクも考慮すべきです。医療費の自己負担割合が変わる節目(70歳、75歳)を見据えて制度を選ぶと、無理のない保険料負担で安定した医療を受けられるでしょう。
8. 制度選びで注意すべき実務的ポイント
実際の手続きやスケジュールにも注意が必要です。
- 任意継続は退職から20日以内に申請が必要
- 国保は退職から14日以内に市区町村で手続き
- 扶養は配偶者の勤務先を通じて速やかに申請
また、退職後は収入の変化により保険料の軽減制度が使える場合があるため、各制度の窓口に確認することが大切です。「知らなかった」で損をする人も少なくありません。
まとめ:安心して医療を受けるために早めの準備を
定年退職後の健康保険は「任意継続」「国民健康保険」「扶養」の3つの選択肢があります。さらに、70歳で自己負担割合が変わり、75歳からは後期高齢者医療制度に自動的に切り替わります。
最適な選択肢は、年金額や家族構成、生活設計によって異なります。退職前からシミュレーションを行い、自分にとってどの制度が有利かを確認しておくことが大切です。
健康保険は老後の安心に直結する重要な制度です。制度の仕組みを理解し、早めに準備することで、定年後も安心して医療を受けられる生活を実現しましょう。