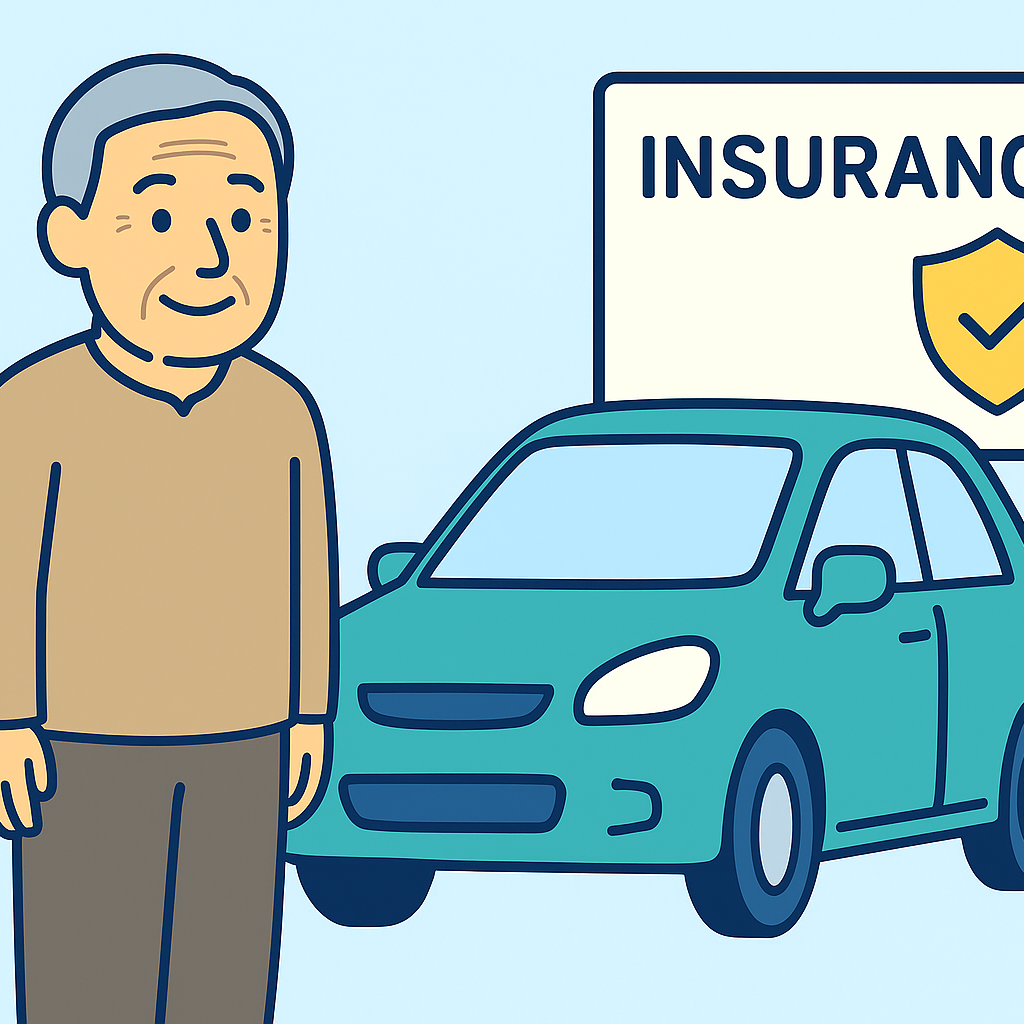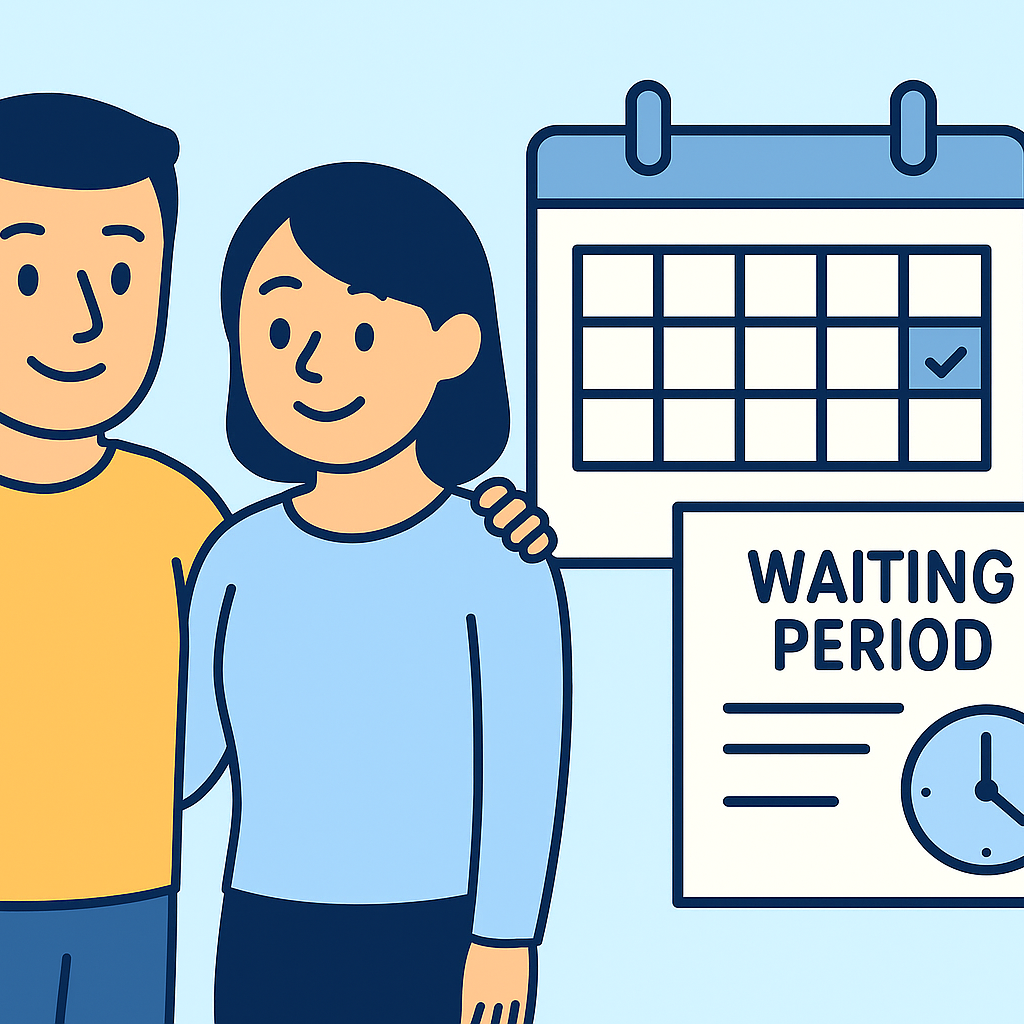はじめに
子どもが生まれた家庭にとって、将来の教育費は大きな関心事です。
大学進学までに必要な教育費は、幼稚園から大学まで公立でも約1,000万円、私立の場合は約2,000万〜2,500万円とも言われています。
こうした長期的かつ高額な支出に備えるため、多くの家庭が「学資保険」を検討します。
学資保険は、毎月一定額を積み立て、子どもの進学時期などのタイミングで一括または分割で受け取れる保険商品です。
貯蓄機能だけでなく、契約者(親)に万一のことがあった場合に保険料の払い込みが免除され、満期時には予定通り保険金を受け取れるという保障機能も備えています。
「貯金だけでは不安」「確実に積み立てたい」という家庭にとって、学資保険は教育資金計画の柱となり得るのです。
1. 教育費の必要額と時期の把握
教育費は一度にかかるものではなく、進学の節目ごとに大きく増減します。
一般的な支出のピークは以下の通りです。
- 幼稚園~高校:毎年一定額(公立か私立かで差が大きい)
- 大学入学時:入学金・授業料・下宿費などで初年度に100万~200万円程度
- 大学在学中:年間授業料に加え、生活費や教科書代、交通費など
教育費の多くは、子どもが18歳前後のタイミングで必要になります。
このため、学資保険の満期時期は大学入学時や高校卒業時に合わせるのが一般的です。
2. 学資保険の基本構造(貯蓄型・保障型)
学資保険は大きく分けて「貯蓄型」と「保障型」があります。
- 貯蓄型:教育資金を計画的に積み立てることを目的とし、返戻率(支払った保険料に対する受取金額の割合)が高め。
- 保障型:貯蓄に加え、医療保障や死亡保障なども付帯しているタイプ。保障が厚い分、返戻率は低下しやすい。
目的が「教育資金の準備」であれば貯蓄型を選ぶのが効率的ですが、医療保障も同時に確保したい場合は保障型も選択肢になります。
3. 返戻率と保険料負担のバランス
学資保険選びで重要なのが「返戻率」です。返戻率は以下の式で求められます。
返戻率(%)=(受取総額 ÷ 支払保険料総額)× 100
例えば、総支払保険料が180万円で、受取総額が200万円なら返戻率は約111%になります。
返戻率は高いほど効率的に資金を増やせますが、支払い方法や契約内容によって変動します。
特に、一括払いや短期払込にすると返戻率は高くなる傾向がありますが、短期間にまとまった資金が必要となるため、家計状況とのバランスを見極める必要があります。
4. 契約者の保障(親の万一時の免除)
学資保険の大きな特徴のひとつが「契約者(親)に万一があった場合の保険料払込免除」です。
契約者が死亡または高度障害状態になった場合、それ以降の保険料の払い込みは不要となり、満期時には予定通り保険金を受け取れます。
この機能によって、教育資金が途中で途切れるリスクを防げるため、家庭にとって大きな安心材料となります。
ただし、免除の条件や範囲は保険会社によって異なるため、契約前に必ず確認しましょう。
5. 途中解約・契約変更時の注意点
学資保険は長期契約が前提のため、途中解約すると元本割れすることが多くあります。
また、契約内容の変更(払込期間短縮、保険金額変更など)によって返戻率が下がる場合もあります。
契約前に、万一支払いが難しくなったときの対応(契約者貸付制度や払済保険への変更など)を確認しておくと安心です。
6. 学資保険と他の積立商品の比較(新NISA・定期預金など)
教育資金の準備は、学資保険だけではありません。最近では、新NISAを利用して株式や投資信託で長期運用する家庭も増えています。
| 商品 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 学資保険 | 元本保証性が高い/契約者の万一時に払込免除がある | 利回りは低め/途中解約すると元本割れの可能性 |
| 新NISA | 年間最大360万円(つみたて枠+成長投資枠)の投資が可能/非課税期間は無期限/運用益・配当が非課税/運用次第で高い利回りが期待できる | 元本割れリスクがある/投資経験や知識が必要/価格変動により短期的な損失の可能性 |
| 定期預金 | 安全性が高い/元本保証がある | 金利が極めて低い/インフレに弱い |
リスクとリターンのバランスを考え、複数の方法を組み合わせるのも効果的です。
7. 加入時期別のおすすめプラン
学資保険は加入時期によって返戻率や保険料が大きく変わります。
- 出産前〜0歳:保険料が最も安く、返戻率も高め。
- 1〜3歳:まだ有利な条件で契約可能。
- 4歳以降:返戻率が低下する傾向があるため、早めの契約が望ましい。
可能であれば出産前後に加入し、長期間かけて無理なく積み立てるのが理想です。
8. まとめ:教育資金計画の柱としての学資保険活用法
学資保険は、確実に教育資金を準備できる有効な手段です。
貯蓄型か保障型かを目的に応じて選び、返戻率と保険料負担のバランスを取りながら契約することが大切です。
さらに、契約者の万一時の払込免除や、他の積立方法との併用も視野に入れることで、より強固な教育資金計画を立てられます。
教育費は子どもの将来を支える大切な投資です。早めの準備と計画的な積立で、安心して成長を見守れる環境を整えましょう。