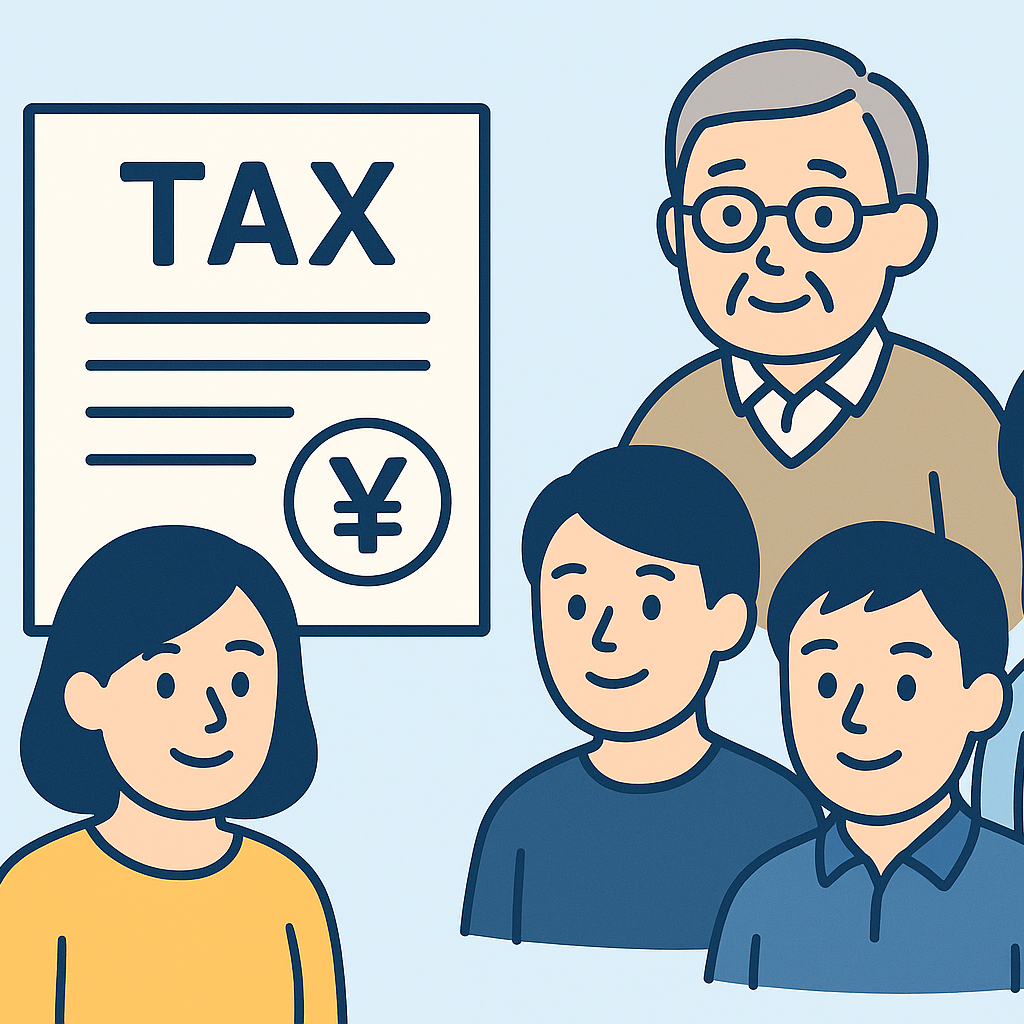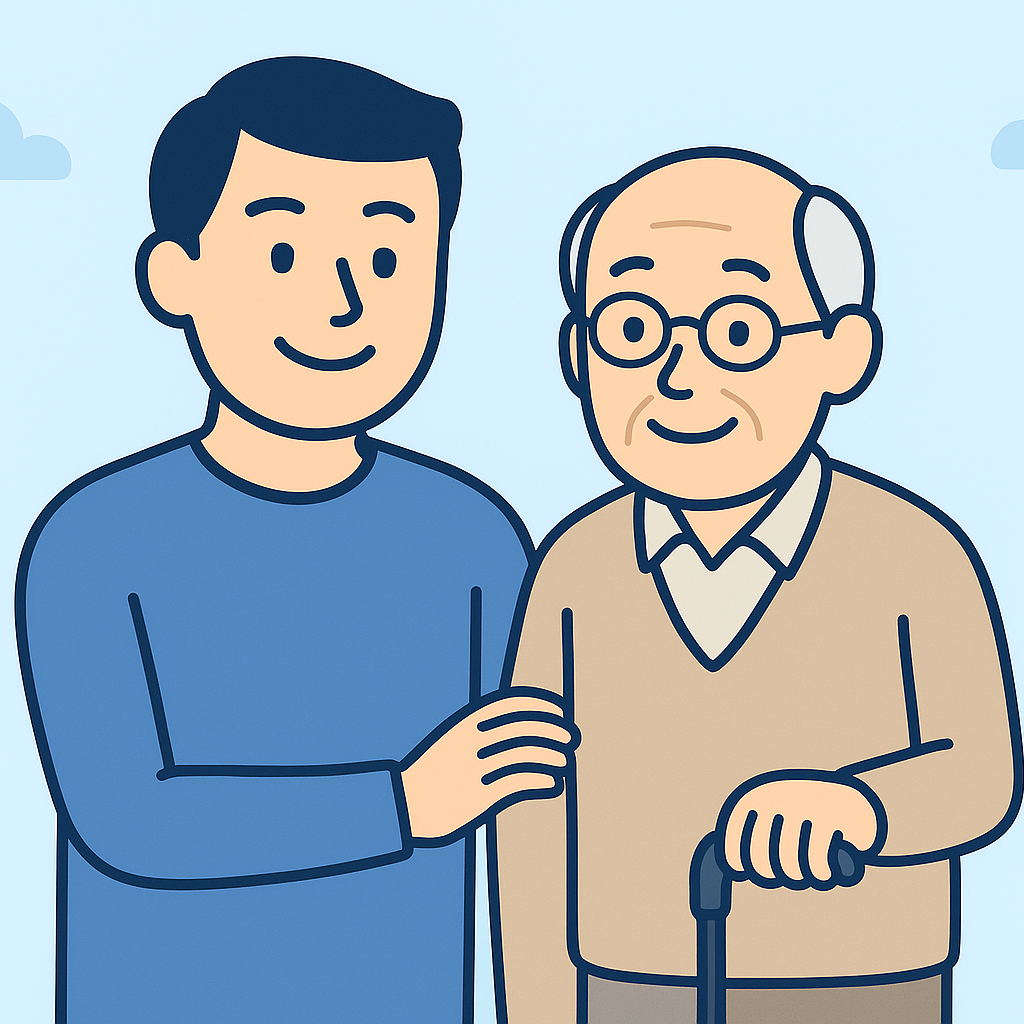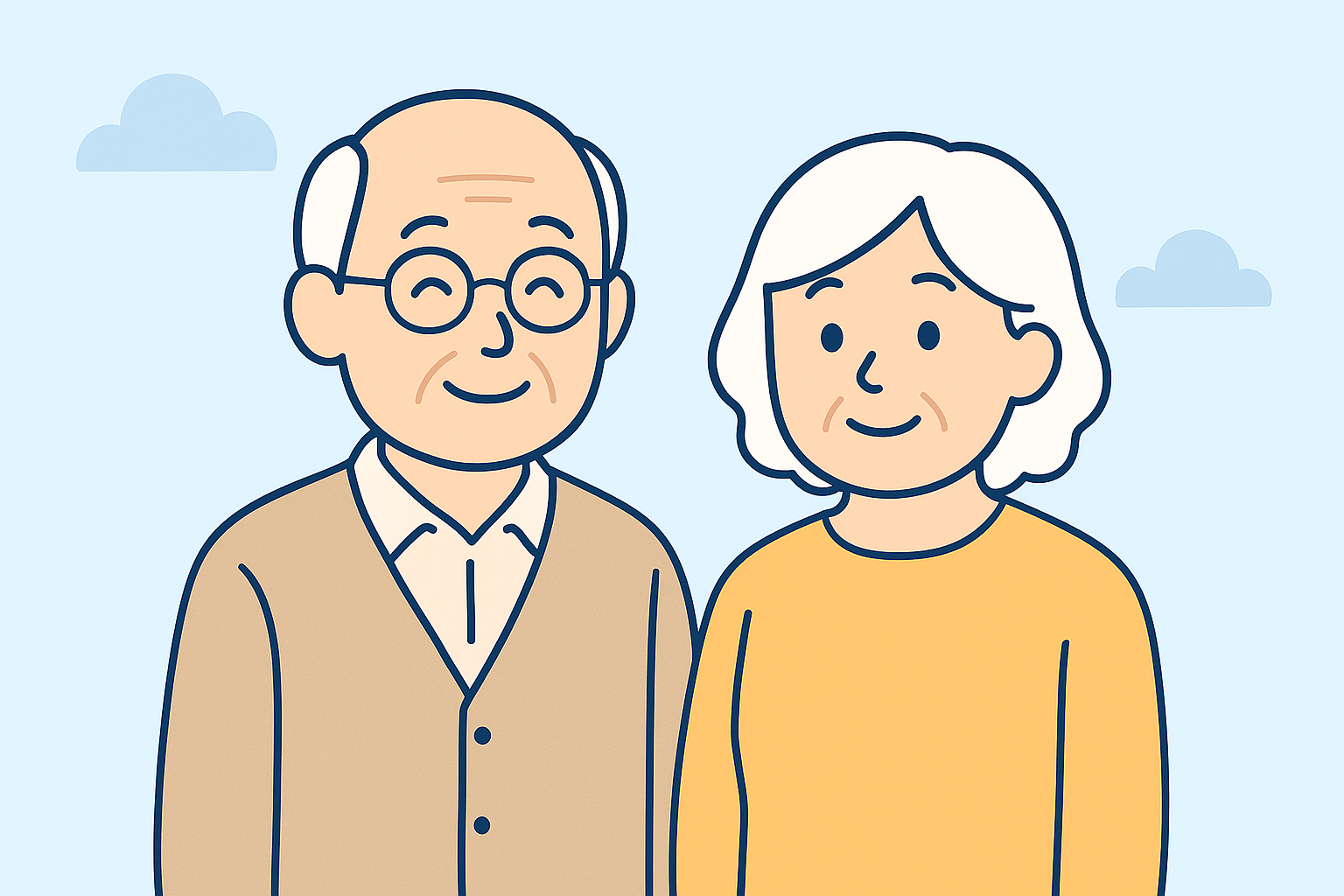
はじめに:配偶者は相続税がほとんどかからない?
相続税の仕組みにおいて、配偶者は非常に優遇されています。法律上の配偶者が相続する財産については、相続税が「法定相続分」または「1億6,000万円」までは非課税になるという「配偶者の税額軽減」という制度があります。この制度は、残された配偶者の生活保障のために設けられており、非常に強力な節税効果を持っています。
しかし、「全部配偶者に相続させれば安心」と思っていると、将来の「二次相続」(配偶者が亡くなったときの相続)で税負担が跳ね上がるというケースも。今回はこの制度の仕組みと活用法、そして二次相続まで見据えた戦略的な相続設計について解説します。
1. 配偶者の税額軽減制度の内容
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産に対して「1億6,000万円」または「法定相続分」までは相続税がかからない、という制度です。このどちらか高い方まで非課税になるため、多くのケースで配偶者の相続税はゼロになります。
たとえば、相続財産が2億円で、配偶者が1億6,000万円を相続する場合、配偶者の相続分については非課税となり、課税対象は他の相続人だけになります。
2. 制度の適用条件と上限(法定相続分 or 1億6,000万円)
この制度が適用されるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 相続税の申告をすること(非課税でも申告が必要)
- 法定相続人である配偶者が実際に財産を取得すること
非課税枠は「法定相続分」または「1億6,000万円」のいずれか高い方。法定相続分とは、民法で定められた配分割合で、たとえば配偶者と子がいる場合は2分の1となります。
3. 遺言との併用・分割協議の影響
遺言書によって「すべて配偶者に相続させる」と指定することも可能です。また、遺産分割協議の結果として配偶者が多くの財産を取得した場合でも、この軽減制度は適用されます。
ただし、遺言の内容によっては他の相続人の「遺留分」を侵害する可能性があり、後々トラブルになるケースも。また、未分割のまま申告を迎えると税額軽減が使えないため、「申告期限内に分割」することが大前提です。
4. 一次相続と二次相続の税負担の違い
一次相続で配偶者がすべてを相続すると、相続税はほぼゼロになります。しかし、配偶者が亡くなったとき、今度は子などがすべての財産を引き継ぐ「二次相続」が発生します。
このとき、配偶者の税額軽減は使えないため、相続税が一気に重くなる傾向があります。また、基礎控除も一次相続より減るため、課税対象額が多くなりやすいのです。
5. 二次相続を見据えた分配の工夫
一次相続であえて子どもに一部の財産を分けておくことで、相続税負担を全体でならすことができます。例えば、配偶者にすべてを相続させるのではなく、一部を子に渡しておけば、配偶者が亡くなったときに残る財産が減るため、二次相続時の課税額を抑えられます。
このように、「配偶者にたくさん渡せるから渡す」のではなく、「家全体としての税負担がどうなるか」を基準に判断するのが賢い方法です。
まとめ:「今」だけでなく「次」も見据えた設計を
配偶者の税額軽減は、非常に強力な相続税の優遇措置です。しかし、そのメリットだけを見て全財産を配偶者に集中させると、将来の二次相続で大きな税負担がのしかかる可能性があります。
相続対策は“部分最適”ではなく“全体最適”で考えるべきです。配偶者が安心して暮らせるようにしつつ、子ども世代への税負担も考慮した配分設計こそが、家族全体にとって本当に意味のある相続となるでしょう。