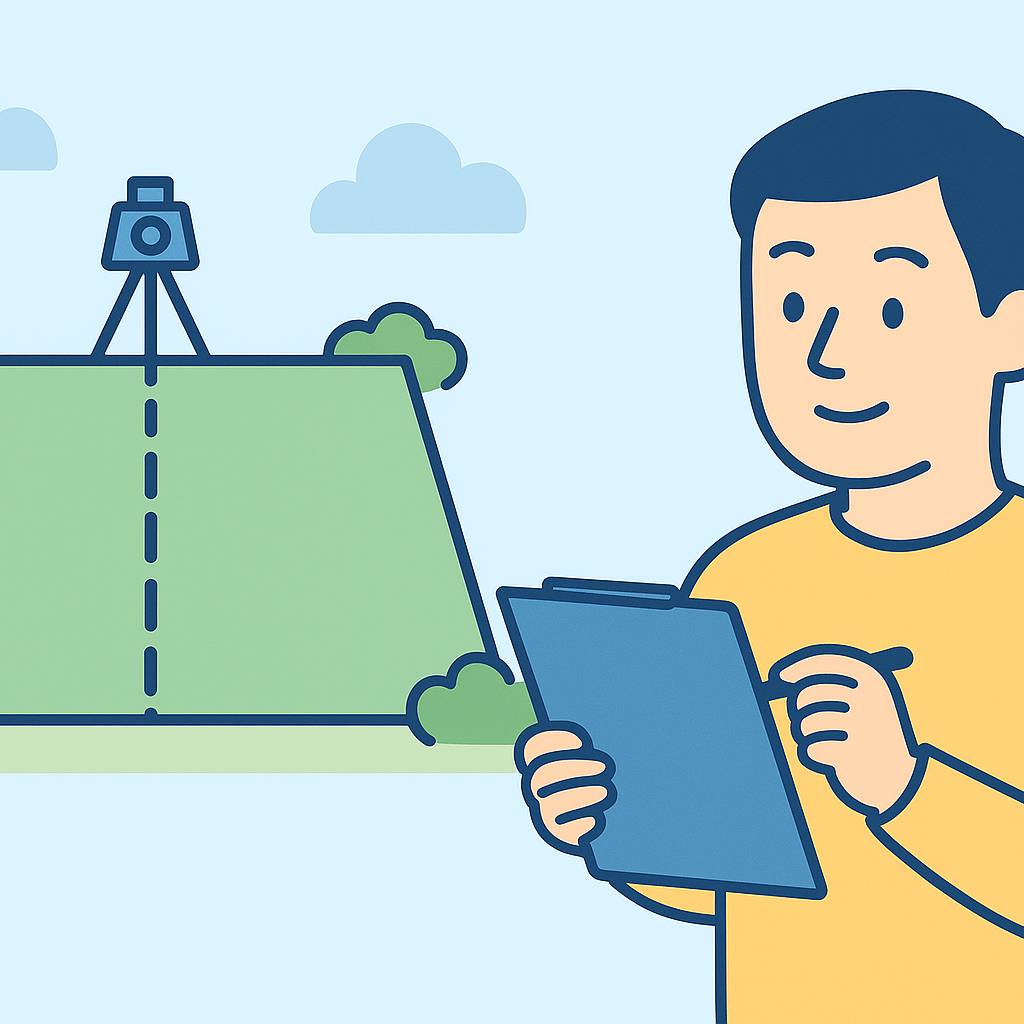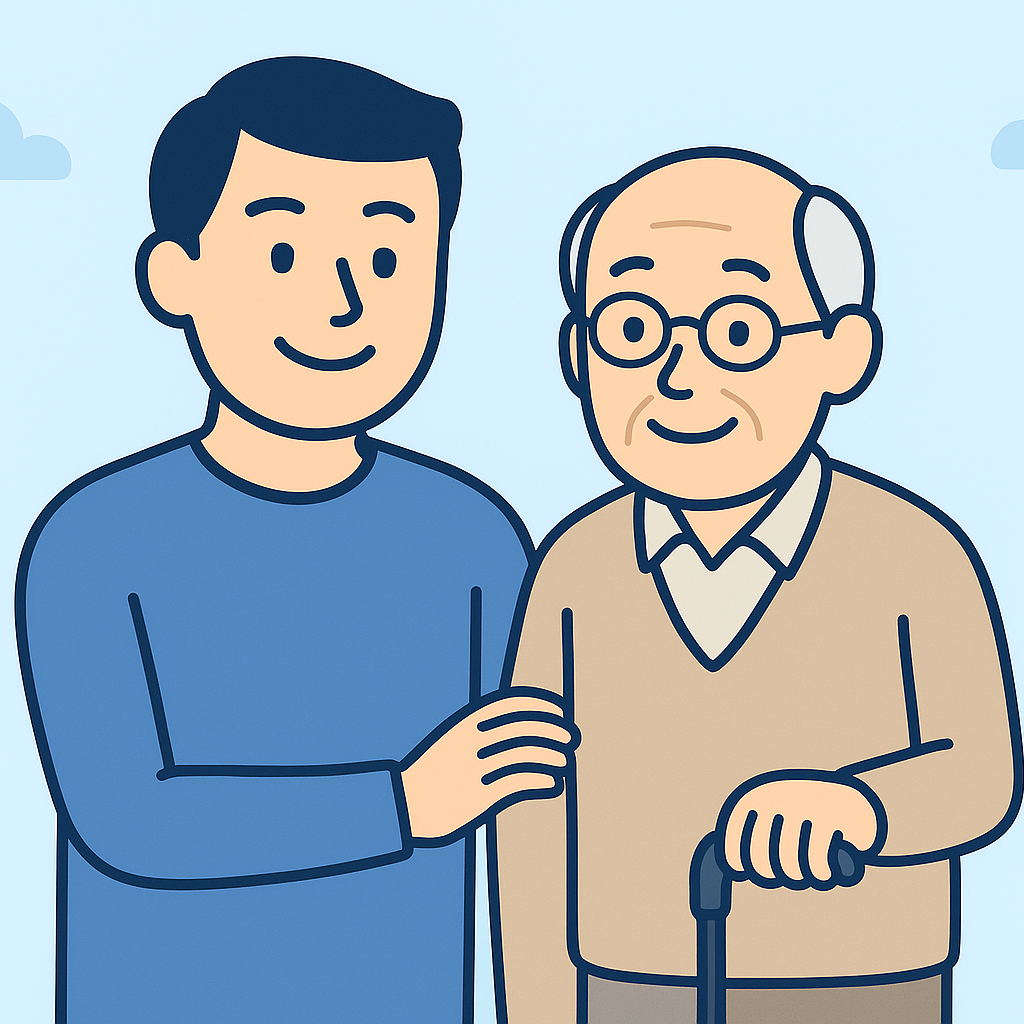はじめに:誰が相続税を申告するのか?
相続が発生すると、「相続税の申告が必要かどうか」をまず確認することが重要です。ただし、すべての相続で申告が必要というわけではありません。実際には、全体の相続のうち約1割程度しか相続税が発生しないと言われています。
これは、相続税には「基礎控除」やさまざまな特例があるため、多くのケースでは課税対象額に達しないからです。しかし、油断は禁物。判断を誤ると「申告漏れ」となり、加算税や延滞税が発生する可能性もあります。
この記事では、申告の要否を見極めるための判断基準と、実際の手続きの流れについて詳しく解説します。
1. 課税の有無を判断するポイント(基礎控除超過)
相続税の申告が必要かどうかは、受け取った財産が「基礎控除額を超えているか」で判断します。基礎控除額は以下の計算式で求めます。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、
→ 3,000万円+600万円×3=4,800万円
この金額を「遺産の課税対象額」が上回っていれば、相続税の申告義務が発生します。
注意したいのは、生命保険や死亡退職金など「みなし相続財産」も含めて判定する点です。現金や預金以外にも資産がある人は、見落としやすいポイントです。
2. 複数人の相続人がいる場合の申告の仕方
相続人が複数いる場合、相続税の申告は原則として「各相続人ごと」に行います。ただし、実務上は代表者が一括して申告書を提出するケースが多く、以下のような流れになります。
- 相続財産全体を評価し、課税遺産総額を算出
- 法定相続分に応じて相続税総額を仮計算
- 各相続人の取得額に応じて個別の税額を計算
- 一括して「相続税申告書」にまとめて提出
なお、相続税は「財産を実際に取得した人」に対して課税されるため、遺言や遺産分割協議によって取得割合が変われば、税額も異なってきます。
3. 申告期限と必要書類の一覧
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。遅れると加算税や延滞税が課されるため、早めの準備が必要です。
申告時に必要となる主な書類は以下の通りです。
- 相続税申告書(第1表〜第15表など)
- 遺産の明細書(財産目録)
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本・住民票・マイナンバー確認書類
- 不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 預貯金の残高証明書
- 株式・投資信託の残高明細
- 生命保険金・死亡退職金の支払通知書
- 遺言書や遺産分割協議書の写し
また、税務署に提出するのとは別に、法務局での相続登記も並行して行う必要がある場合があります。
4. 税理士への依頼と自力申告の比較
相続税の申告は、自力でも可能ですが、多くの人が税理士に依頼しています。理由は以下の通りです。
【税理士に依頼するメリット】
- 財産評価の正確性が高くなる(特に不動産や非上場株式)
- 特例の適用可否や節税スキームに強い
- 申告ミスや漏れを防げる
- 家庭裁判所との手続きが必要な場合のアドバイスも可能
【自力申告の注意点】
- 申告書の作成が複雑(添付書類も多い)
- 財産評価の誤りで税務調査の対象になることも
- 特例の適用漏れで損をするリスクが高い
費用相場としては、相続財産5,000万円程度で20万〜40万円が目安とされています。
5. 遺産評価と財産目録の作成方法
相続税の計算の前提として、すべての財産の価値を「円換算」で評価する必要があります。これを「遺産評価」と呼び、その結果を一覧にまとめたものが「財産目録」です。
【主な評価方法】
- 現金・預金:残高証明に基づき評価
- 不動産:路線価方式または固定資産税評価額で評価
- 上場株式:相続日または前後数日の終値平均で評価
- 生命保険金:支払金額ベース
財産目録は、相続人間の協議や税務署への申告のベース資料となるため、正確かつ網羅的に作成する必要があります。
6. 申告漏れと加算税・延滞税のリスク
相続税の申告で最も避けたいのが「申告漏れ」です。意図せずに課税対象の財産を申告から除いてしまった場合、税務署の調査により発覚し、以下のペナルティが課される可能性があります。
- 過少申告加算税(10〜15%)
- 無申告加算税(15〜20%)
- 重加算税(35〜40%)※仮装・隠蔽がある場合
- 延滞税(年利7.3%→最終的に2.5%)
特に、預貯金の移動履歴や生命保険の加入履歴は税務署に把握されやすく、調査対象となることが多いです。後から気づいても時すでに遅し、ということも。
まとめ:対象かどうか、早めに確認が鉄則
相続税の申告は、一部の資産家だけの問題と思われがちですが、生命保険や不動産を含めると意外と基礎控除を超えてしまうケースもあります。そのため、相続が発生したらまず「課税対象かどうか」を冷静に確認することが必要です。
そして、期限内の申告と納付をスムーズに行うためには、事前の準備と専門家の協力が不可欠です。複雑な相続を乗り越えるためにも、申告要否の判断から丁寧に進めていきましょう。