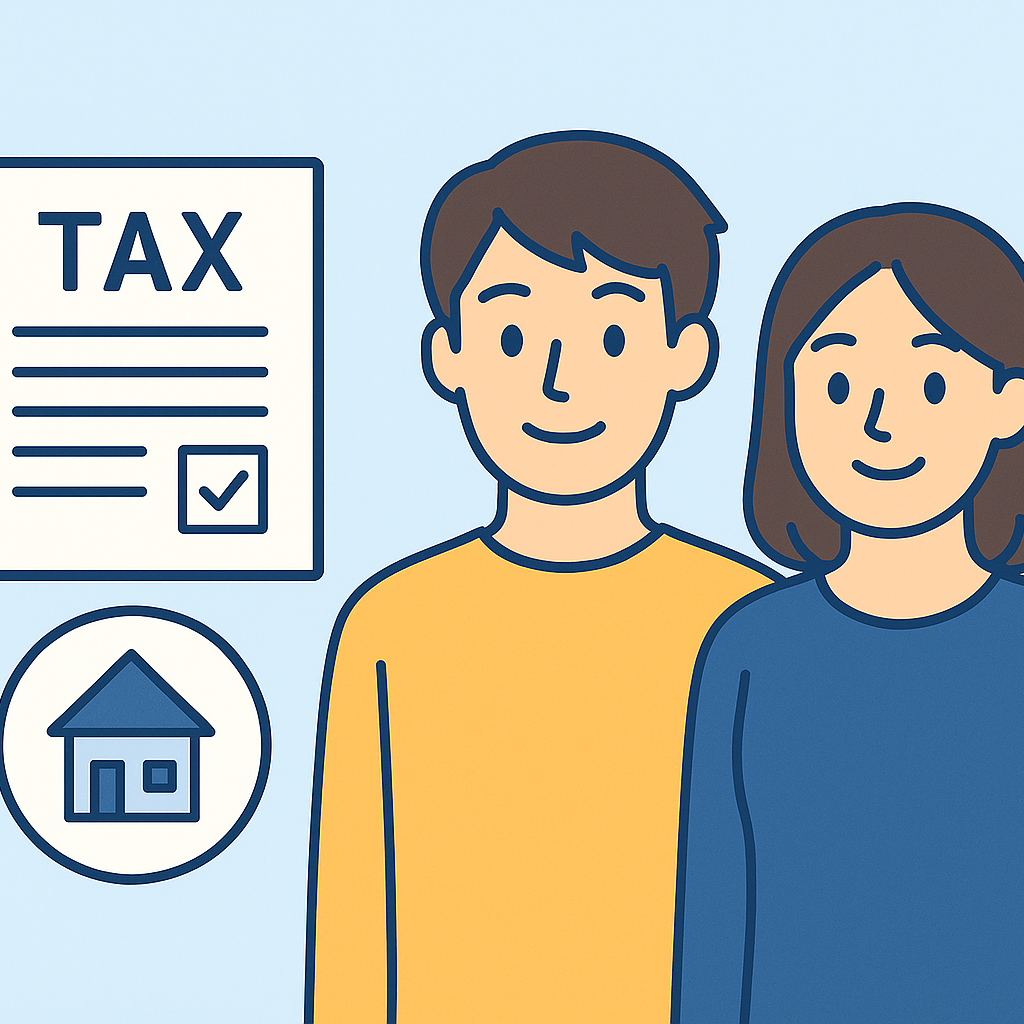はじめに:実家を相続した後の悩みとは
親が亡くなり、実家を相続することになった――多くの人が直面する人生の大きな節目です。しかし、いざ相続すると「住む予定はない」「売るべきか保有すべきか決められない」と悩むケースが少なくありません。
特に都市部から離れた実家や高齢化が進む地域の住宅は、流通性が低く、売却も簡単ではないことが多いのが実情です。また、空き家のまま放置すると、固定資産税の負担や資産価値の下落、さらには近隣トラブルの火種にもなりかねません。
相続後の選択肢には、「売却」「活用(賃貸・転用)」「保有・管理」の3つがあります。それぞれのメリット・デメリットを把握し、感情と経済性のバランスを取った判断が求められます。
1. 売却する場合の手続きと査定の流れ
最もシンプルな選択肢は、「売却して現金化する」ことです。売却には以下のようなステップが必要です。
- 相続登記を完了させて名義を変更
- 不動産会社に査定を依頼(複数社が望ましい)
- 媒介契約の締結と売却活動
- 買主との売買契約、決済・引渡し
注意すべきは、売却益が出た場合には譲渡所得税が発生する点です。ただし、実家を売る際には「空き家の3,000万円特別控除」などの優遇措置もあるため、事前に税理士や不動産会社に相談するのが賢明です。
2. 賃貸として活用する場合のメリット・リスク
実家に誰も住む予定がないが、売ることにも抵抗がある――そんな場合は、賃貸として活用する選択肢があります。毎月の家賃収入が見込めるほか、空き家リスクも軽減できます。
一方で、築年数の古い住宅はリフォームが必要だったり、借り手がつかない可能性もあります。また、入居者との契約や管理の手間、将来的な退去リスクなども見据えておくべきです。
賃貸化する際は、地元の不動産管理会社と提携し、家賃設定や空室率の見込みを確認した上での判断が必要です。
3. セカンドハウス・民泊・店舗転用という選択肢
最近では実家を「セカンドハウス」や「民泊」「店舗」などに転用するケースも見られます。特に観光地や交通アクセスの良いエリアでは、有効な選択肢となることもあります。
民泊として貸し出すには、住宅宿泊事業法(民泊新法)への届出や、消防法上の対応が必要です。また、店舗や事務所として使う場合は用途地域の確認も欠かせません。
転用の可能性は物件の立地・構造に大きく左右されるため、地域の不動産市場や法律面の条件をよく確認したうえで計画することが必要です。
4. 維持管理費用と固定資産税の負担
「とりあえず保有しておこう」と考えた場合でも、維持管理の負担は避けられません。空き家であっても以下のようなコストが発生します。
- 固定資産税(都市部なら年数十万円規模も)
- 水道光熱費の基本料金
- 修繕・草刈り・清掃などの維持管理費
- 防犯・防災対策(巡回警備、火災保険など)
これらを長期的に負担できるかは、他の相続財産や家族の同意とも関係してきます。維持コストが年単位でかさむことを見込んで、放置ではなく明確な管理体制を構築することが重要です。
5. 「誰が住むのか」「誰が管理するのか」の明確化
実家を保有するにしても、誰が責任をもって管理するかを明確にしておかなければ、将来的にトラブルになるリスクが高くなります。
よくあるのが、「兄弟の誰かがそのうち住むかもしれない」「将来まで相談保留」という曖昧な状態のまま数年が過ぎ、最終的に空き家化・老朽化してしまうケースです。
相続人の中で誰が主導して管理・活用・売却を進めるのか。賃料や売却益が出た場合はどう分けるのか。感情的なもつれが起きる前に、早めに合意形成を図ることが不可欠です。
6. 放置による資産価値低下と空き家指定リスク
実家を放置してしまうと、建物の老朽化が進むだけでなく、近隣住民や行政からの指導対象になる恐れもあります。
「特定空き家」に指定されると、以下のような措置を受ける可能性があります。
- 固定資産税の住宅用地特例(最大1/6)適用外になる
- 行政代執行による解体・費用負担
- 建物倒壊や害虫・不審者などによる近隣苦情
価値を維持するためにも、空き家化を防ぎ、定期的な見回りや管理委託を行うことが求められます。
まとめ:実家の相続は“感情”と“経済性”の両面から判断を
実家の相続は、単なる不動産の継承以上に、家族の感情・思い出・経済的判断が交錯する難しいテーマです。
「親の思い出があるから手放したくない」「でも維持費が高すぎる」「誰も住まないのに残す意味があるのか」――そうした悩みは、多くの相続人が共有するリアルです。
重要なのは、「なんとなく保有」や「そのまま放置」という選択をせず、経済的な視点での収支シミュレーションと家族の合意形成を早めに行うこと。そのうえで、売却・賃貸・転用・保有の中から最適な選択肢を導き出しましょう。