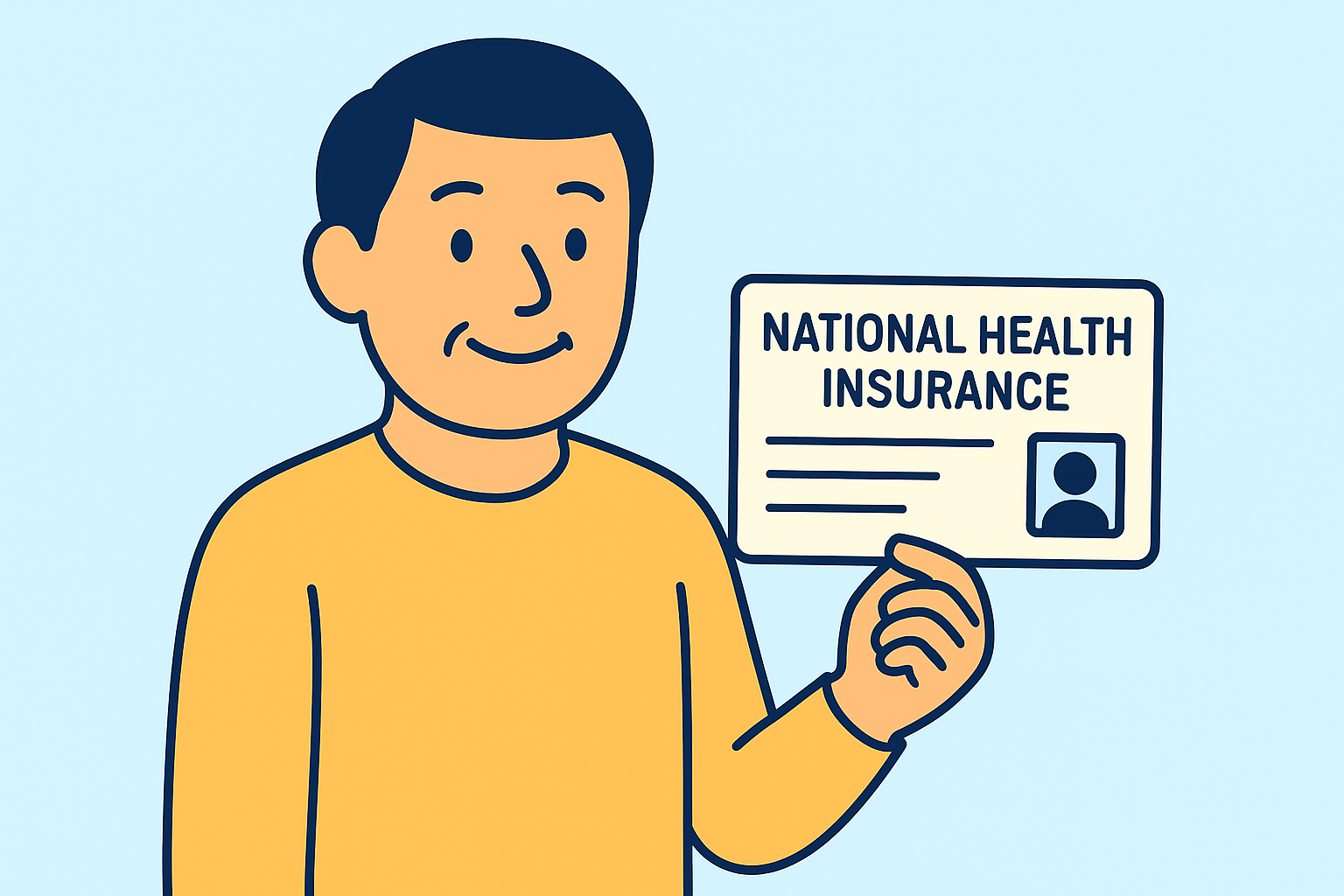
はじめに:高額になりやすい国保料を軽減するには
国民健康保険(国保)は、自営業者やフリーランス、退職後に会社の健康保険を任意継続しなかった人などが加入する医療保険制度です。会社員が加入する社会保険と比べると、保険料の算定方法が異なり、世帯単位で計算されるため、所得がある程度ある世帯では負担が大きく感じられることも少なくありません。
しかし、国保には「軽減措置」や「減免制度」などの仕組みが用意されており、条件に当てはまれば保険料を下げることが可能です。本記事では、国民健康保険料の仕組みと、安くするために知っておきたい制度について整理していきます。
1. 国民健康保険料の内訳(医療分・支援分・介護分)
国民健康保険料は大きく3つの区分に分けられています。
- 医療分保険料:加入者の医療費に充てられる部分。
- 後期高齢者支援金分:75歳以上の後期高齢者医療制度を支えるための拠出金。
- 介護分保険料:40歳から64歳の人が負担する介護保険料。
市区町村ごとに細かな計算方法は異なりますが、これらを合算したものが「国保料」として請求されます。特に介護分は年齢によって負担が生じるかどうかが変わる点に注意が必要です。
2. 所得割・均等割・平等割の仕組み
国保料は大きく以下の3つの仕組みで計算されます。
- 所得割:前年の所得に応じて計算される部分。所得が高いほど保険料が上がります。
- 均等割:加入者1人あたりに一律で課される保険料。家族の人数が多いほど負担が増します。
- 平等割(世帯割):世帯ごとに一律で課される保険料。所得や人数に関係なく発生します。
このように、単純に所得だけではなく、世帯人数や構成によっても国保料が大きく変わります。特に子どもが多い世帯では均等割の負担が大きくなりがちです。
3. 所得が少ない世帯への軽減措置
国民健康保険には、所得が一定以下の世帯に対して応益分(均等割・世帯割)を軽減する制度があります(所得割などの応能分は対象外)。
軽減の区分と対象(応益分のみ)
- 7割軽減(均等割・世帯割の70%を減額)
- 5割軽減(同 50%を減額)
- 2割軽減(同 20%を減額)
判定の考え方(基準所得額を下回ると軽減)
軽減の可否は世帯の総所得金額で判定します。おおむね次の基準所得額を下回ると軽減が適用されます(年度・自治体で係数は若干異なります)。
| 軽減割合 | 判定の目安(基準所得額) | 3人世帯の給与収入目安※ |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円 以下 | 約98万円 以下 |
| 5割軽減 | 43万円 +(被保険者数×29万円) 以下 | 約197万円 以下 |
| 2割軽減 | 43万円 +(被保険者数×53.5万円) 以下 | 約302万円 以下 |
※例:夫婦(40歳)+子1人、給与収入のみの世帯を想定した概算。実際の判定は控除や所得区分により変動します。
※世帯内の給与・年金所得者が2人以上の場合は、43万円に10万円×人数などの加算が入る取扱いがあります(自治体要綱に準拠)。
未就学児の均等割は原則5割軽減
子育て支援の観点から、未就学児に係る均等割は原則として公費で5割軽減されます(自治体実施)。
これらの軽減によって、非課税世帯や低所得世帯では均等割・世帯割が大幅に減額され、国保料負担を抑えられます。
4. 減免制度の条件と申請方法
災害や失業、事業の大幅な収入減少などで生活が困難になった場合には、保険料の「減免制度」を利用できることがあります。
代表的な減免理由は以下の通りです。
- 災害で住宅や財産に損害を受けた場合
- 失業や休業で収入が大幅に減った場合
- 特別な事情で納付が困難になった場合
申請には、市区町村の窓口での手続きが必要で、収入状況や被災状況を証明する書類(給与明細、罹災証明書など)を提出する必要があります。
5. 失業者への特例軽減制度
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けている人は、「前年所得を30/100としてみなす」特例が適用され、国保料が軽減される仕組みがあります。これにより、前年に収入が多かった場合でも、失業後の所得が減っている実態に合わせて保険料が計算されます。
6. 学生や低所得者が利用できる制度
学生やフリーターなど収入が少ない人の場合、世帯分離をして自分の所得のみで判定されるようにすると、軽減制度が適用されやすくなることがあります。
また、非課税世帯であれば大幅な軽減が受けられる可能性が高いため、自分がどの区分に該当するのかを早めに確認しておくことが大切です。
7. 支払い方法(口座振替・分割)での工夫
国保料の軽減とは直接関係ありませんが、支払い方法を工夫することで家計の負担を軽くできます。
- 口座振替:振込忘れを防ぎ、延滞金のリスクを避けられる。
- 年払い・期別払い:まとめて支払うか、分割で支払うかを選択できる。
- クレジットカード払いや電子マネー払い:一部の自治体ではポイント還元が受けられる場合もある。
支払い方法を見直すことで、精神的な負担も軽減できます。
8. 他制度(高額療養費など)との併用で負担軽減
国保の保険料自体を下げる制度に加えて、医療費が高額になったときに「高額療養費制度」や「限度額適用認定証」を利用すれば、実際に支払う医療費の自己負担を減らすことができます。こうした制度と組み合わせることで、トータルの負担を大幅に軽減できる可能性があります。
まとめ:申請しなければ受けられない軽減制度を知っておこう
国民健康保険料は、所得や世帯構成に応じて大きく変わり、時に高額となることがあります。しかし、低所得世帯への軽減、失業者への特例、災害や収入減少による減免など、負担を減らす制度は数多く用意されています。
重要なのは「自分から申請しなければ適用されない制度が多い」という点です。加入者が制度を知らずに申請しなければ、本来受けられるはずの支援を逃してしまいます。国保に加入している方は、自分や世帯がどの制度の対象になるのかを必ず確認し、必要であれば速やかに申請して活用しましょう。




