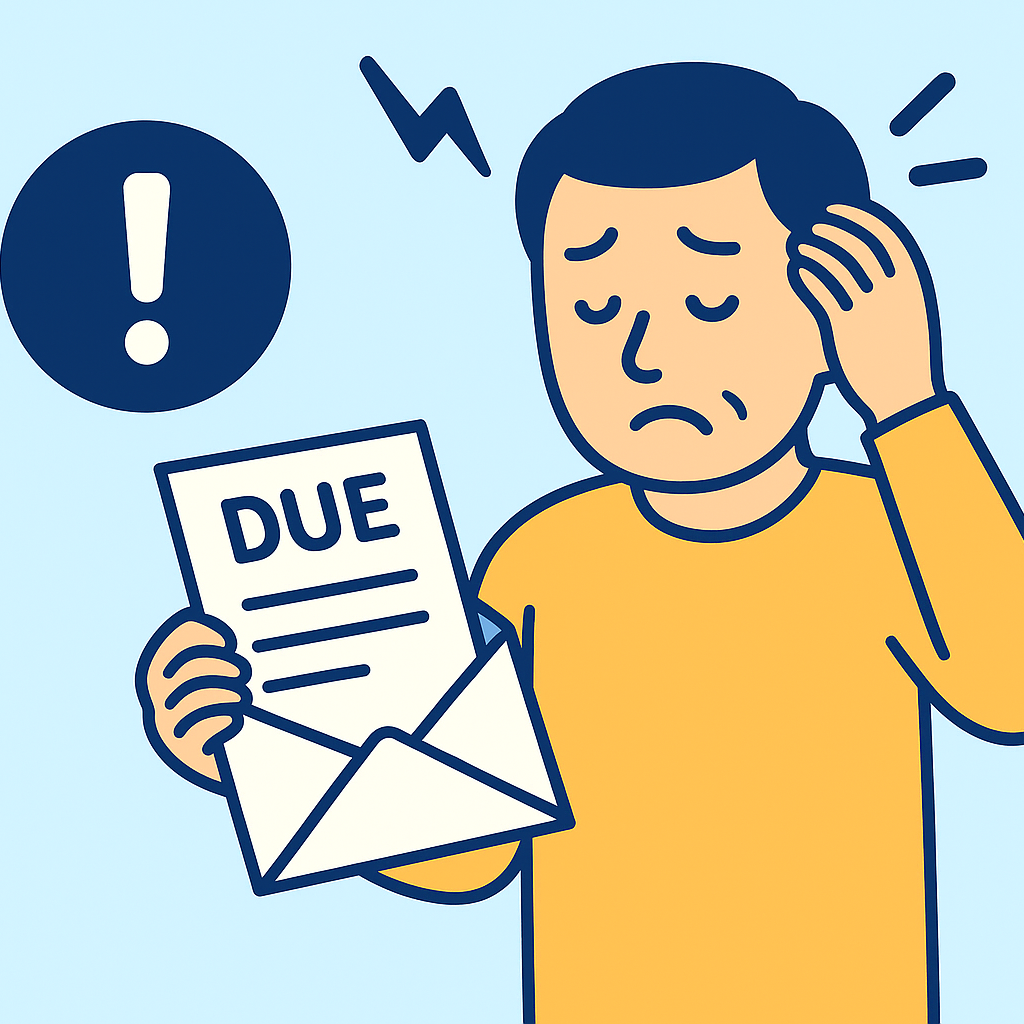はじめに:年収の壁を理解することが家計に直結
「扶養に入っているかどうか」で家計の負担は大きく変わります。特にパートやアルバイトをしている配偶者や学生の子どもにとっては、収入が一定額を超えると扶養から外れ、健康保険料や税金を自分で負担する必要が出てきます。いわゆる「年収の壁」を意識せずに働くと、せっかく収入が増えても手取りが減ってしまうことがあります。
この記事では、健康保険や税制における扶養の条件、そしてそれぞれの年収基準の違いや注意点について整理していきます。
1. 健康保険の扶養条件(年収130万円基準)
まず押さえておきたいのは、健康保険における扶養条件は「年間収入130万円未満」という基準です。
具体的には、今後の収入見込みが月額108,333円未満であれば、配偶者や子どもなどは被扶養者として認定され、保険料を支払わずに医療保障を受けられます。
ただし、被扶養者の収入が被保険者本人(会社員)の収入の半分以上ある場合は扶養に入れません。
2. 60歳以上・障害者の場合の基準(180万円)
例外として、60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満であれば被扶養者として認められます。
これは高齢者や障害者の生活実態を考慮して緩和されている制度です。たとえば年金収入がある高齢の親を扶養に入れる場合、180万円未満であれば加入できる可能性があります。
3. 会社員の配偶者控除・税制上の年収の壁(103万円・150万円・201万円など)
「扶養の壁」というとき、健康保険と並んでよく話題にされるのが税金面での扶養控除や配偶者控除です。こちらは基準が複数あり、混乱しやすいポイントです。
- 103万円の壁:配偶者控除を受けられるかどうかの基準。配偶者の年収が103万円以下であれば、夫(または妻)の所得税が軽減されます。
- 150万円の壁:配偶者特別控除が段階的に減額される開始ライン。年収が150万円を超えると控除額が減っていきます。
- 201万円の壁:配偶者特別控除が完全になくなるライン。ここを超えると税制上の扶養には入れません。
4. 健康保険と税制上の扶養の違い
ここで整理すると、
- 健康保険 → 年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)
- 税制上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除) → 年収103万円・150万円・201万円などが壁
というように、基準額が異なります。そのため「税金の上ではまだ控除があるけど、健康保険では扶養から外れる」あるいは「健康保険は扶養のままでも、税金控除はなくなる」ということが起こり得ます。
5. パート・アルバイト収入の扱い
パートやアルバイトの場合も、収入基準を超えれば扶養から外れる対象となります。時給×労働時間の合計で計算されるため、労働時間を増やすとあっという間に壁を超えてしまうこともあります。
また、社会保険適用拡大によって、従業員数101人以上(2024年10月以降は51人以上)の会社で週20時間以上働くと、年収が106万円を超えた時点で自分の社会保険に加入しなければならなくなります。この場合、130万円の壁より前に扶養から外れることになります。
6. ボーナス・一時収入の影響
見落としがちなのが、ボーナスや一時的な収入です。
健康保険の年収判定は「見込み収入」であり、給与だけでなく賞与や副業収入も含めて合計で判断されます。例えばパート収入が月10万円程度でも、年末にボーナスが出て年収が130万円を超えると扶養から外れる可能性があります。
副業での報酬、原稿料、フリーランスの収入なども対象になるため注意が必要です。
7. 扶養から外れるとどうなるか(保険料負担増)
扶養から外れると、自分で健康保険に加入する必要が出てきます。選択肢は以下の2つです。
- 勤務先で社会保険に加入する(条件を満たす場合)
- 国民健康保険に加入する
どちらにせよ、保険料は全額自己負担になります。例えば国民健康保険料は所得に応じて算定されるため、年間数十万円かかるケースもあります。これまでゼロだった保険料負担が一気に増えるため、収入増加分より負担増の方が大きいという逆転現象も起こり得ます。
8. 収入調整の工夫と注意点
扶養から外れないようにするためには、働き方や収入を調整する工夫も考えられます。
- 月収が基準を超えそうな場合は勤務時間を調整する
- ボーナスを含めて年間収入を見込んでシフトを組む
- 副業収入や臨時収入も合算されることを念頭に置く
ただし、「扶養にとどまるために働く時間を減らす」ことが必ずしも得策とは限りません。長期的に見れば、保険料負担が増えても社会保険に加入した方が将来の年金額が増えるなどのメリットもあります。
まとめ:扶養の壁を理解して働き方を計画する
扶養に入れるかどうかは、健康保険と税制の両面で異なる基準があります。
- 健康保険では130万円(高齢者や障害者は180万円)
- 税制上では103万円、150万円、201万円など段階的に変化
パートやアルバイト、ボーナス、副業収入などが影響するため、年間の見込みを把握しながら働き方を調整することが大切です。一方で、収入が増えて社会保険に加入することが将来的には有利になる場合もあります。短期的な手取りにとらわれず、長期的な家計の安定とライフプランに沿った判断をしていきましょう。